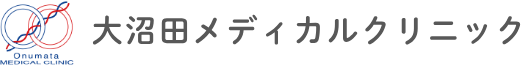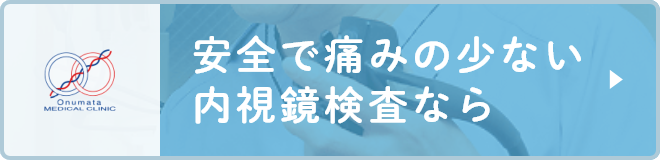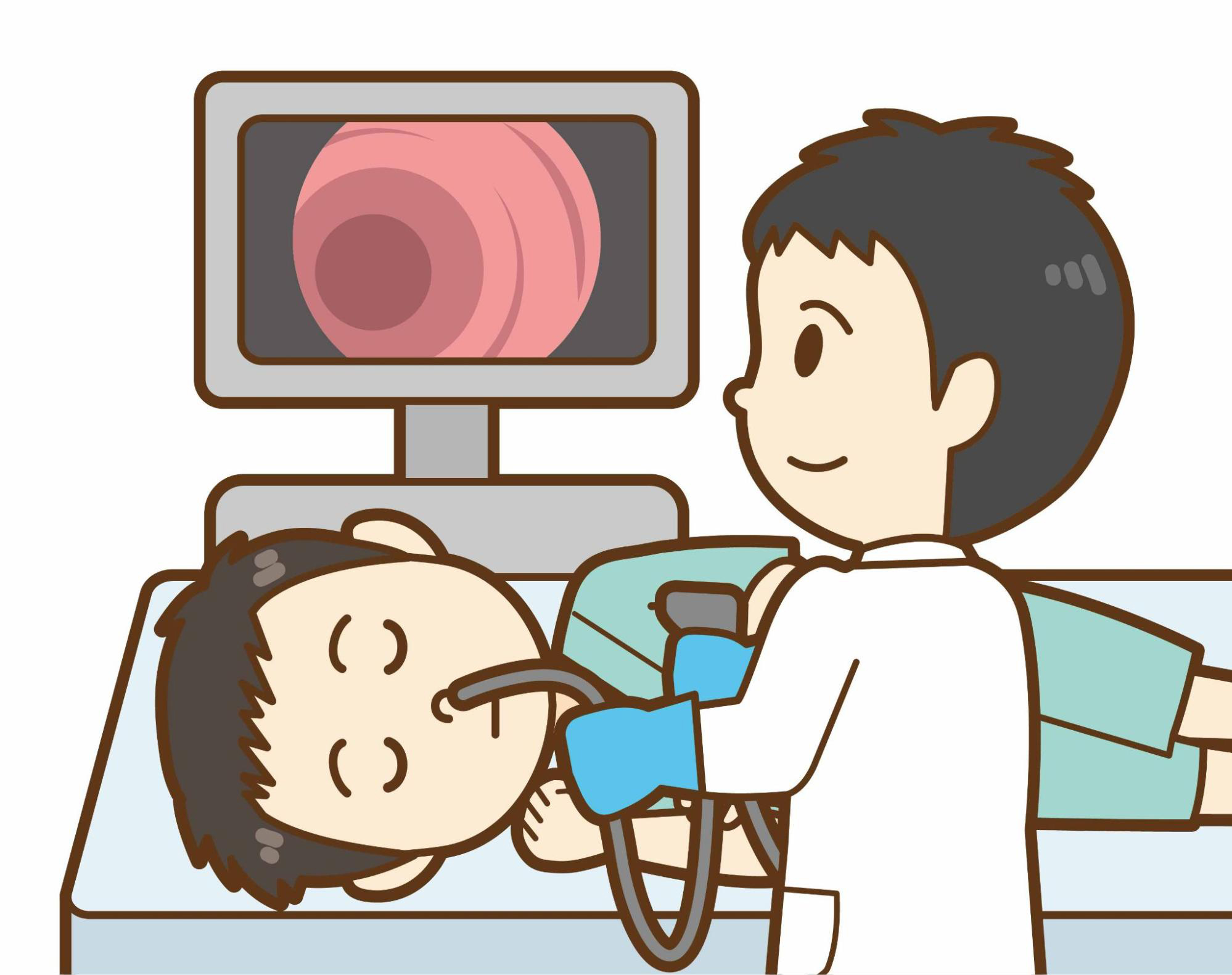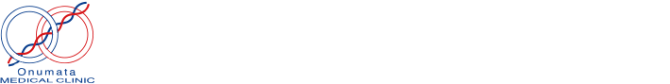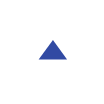逆流性食道炎の症状を抑える寝方とは?生活習慣のポイントも解説

目次
逆流性食道炎は何らかの原因によって胃酸が逆流し、食道に炎症を起こしてしまう病気です。特に寝ているときに胃酸が逆流しやすくなるため、寝るときの姿勢に気を配る必要があります。
この記事では、逆流性食道炎の症状を抑える寝方について詳しく解説します。症状を改善する生活習慣のポイントやよくある質問などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
逆流性食道炎とは

逆流性食道炎とは、胃酸が食道へ逆流し、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。
日本では食生活の変化や生活習慣の影響で患者数が増加しており、特に高脂肪食の摂取や肥満、ストレスなどが関与しています。
ここでは逆流性食道炎の原因や主な症状、なりやすい人の特徴などについて解説します。
逆流性食道炎の原因
逆流性食道炎の主な原因は、下部食道括約筋の緩みと胃酸の過剰分泌です。
食道と胃の境目には下部食道括約筋という筋肉があり、これが胃酸の逆流を防いでいます。しかしさまざまな要因によってこの筋肉が緩むと、胃酸が食道に逆流し、炎症を引き起こすことがあるのです。
下部食道括約筋が緩む原因としては、加齢による老化、胃内圧の上昇、腹圧の上昇、高脂肪食などが挙げられます。
胃内圧の上昇の原因となるのが、食べ過ぎや早食いといった食習慣です。
またストレスによる自律神経の乱れは、胃酸の過剰分泌を引き起こすことがあります。
このようにさまざまな要因によって下部食道括約筋が緩んだり胃酸の分泌量が増えたりすることで、胃酸が逆流しやすくなってしまうのです。
逆流性食道炎の主な症状
逆流性食道炎の主な症状は、胸やけと呑酸(酸っぱいものが口まで上がってくる感じ)です。
前屈みになり、腹圧が上昇することで胃酸が逆流しやすい状態になると、これらの症状が強くなる傾向にあります。
またそのほかにも、げっぷがたくさん出る、食べ物が喉につっかえる感じがする、喉がイガイガする、声枯れ、食後の胃の不快感、早期膨満感(すぐにお腹いっぱいになる)などの症状が現れる場合もあります。
逆流性食道炎になりやすい人
逆流性食道炎になりやすい人の特徴として、以下が挙げられます。
- 食べ過ぎや早食いの習慣がある人
- 脂っこいものを好んで食べる人
- 食べてすぐに寝る習慣がある人
- アルコールや炭酸飲料をよく飲む人
- 喫煙習慣がある人
- 肥満体型の人
- ベルトやコルセットなどでお腹を締め付けることが多い人
- 農業など長時間前かがみの姿勢になる仕事をしている人
- 猫背の人
上記のようにバランスの偏った食生活を送っている人や胃に悪い生活習慣のある人、腹圧を上げる姿勢になっている人は胃酸が逆流しやすいため注意が必要です。
逆流性食道炎の症状を抑える寝方

逆流性食道炎を発症している人は、横になると胃酸が逆流し、睡眠の質が低下してしまうことがあります。
逆流性食道炎患者のおよそ80%が夜間の逆流の影響を受けているとされており、寝ているときの姿勢は症状緩和のための重要なポイントとなります。
逆流性食道炎の症状を抑える寝方として、以下の3つのポイントを押さえることが大切です。
- 体の左側を下にして寝る
- 頭と上半身を高くする
- お腹を圧迫しない服装や姿勢で寝る
ここでは上記3つのポイントについてそれぞれ解説します。
体の左側を下にして寝る
逆流性食道炎では、体の左側を下にして寝ることが大切です。
体の右側を下にして寝ると、胃の位置や形状の関係により、胃酸が逆流しやすくなってしまいます。体を左側にして寝ることで胃の位置が食道よりも低くなり、胃酸の逆流が少なくなります。仰向けで寝るのも、体の右側を下にするよりも逆流が少なくなるため、ぜひ試してみてください。
頭と上半身を高くする
横になっているときの胃酸の逆流を防ぐためには、頭と上半身を高くするのがポイントです。上半身を高くして傾斜をつけることで、胃酸が逆流しにくくなります。枕を2~3個程重ねたり、上半身から枕の下までにかけてタオルを敷いたりするなどして、頭と上半身が高い状態にしてみましょう。
ただしこのような状態を作ると、人によっては肩こりや腰痛を引き起こす場合もあるため、無理のない範囲で試してみてください。
お腹を圧迫しない服装や姿勢で寝る
逆流性食道炎の夜間の症状を抑えるためには、お腹を圧迫しない服装や姿勢で寝ることが大切です。
お腹を圧迫すると腹圧が上昇し、胃酸が逆流しやすくなってしまいます。パジャマはお腹を締め付けないゆったりとしたものを選び、リラックスできる姿勢で寝ましょう。
逆流性食道炎を改善する生活習慣のポイント

逆流性食道炎を改善する生活習慣のポイントは以下の通りです。
- 肥満を改善し適正体重を維持する
- ゆっくりよく噛んで食べる
- 腹部を締め付ける服装は避ける
- 寝る2~3時間前までに食事を済ませる
- バランスの良い食生活を心がける
- 胃酸を増やす食事は控える
ここでは上記6つのポイントについてそれぞれ解説します。
肥満を改善し適正体重を維持する
逆流性食道炎を改善するためには、肥満を改善して適正体重を維持することが大切です。
肥満体型の方は内臓脂肪がたくさんついているため、自然と腹圧が上昇し、胃酸が逆流しやすい状態になってしまいます。そのため現在肥満体型の方は、ダイエットをして体重を減らし、適正体重を目指しましょう。
ダイエットの基本は栄養バランスの良い食事をすることと、毎日適度に運動することです。適正体重まで減らして終わりではなく、規則正しい生活習慣を心がけ、適正体重を維持しましょう。
ゆっくりよく噛んで食べる
逆流性食道炎の原因として、食べ過ぎや早食いが挙げられます。
特に早食いをすると空気も多く飲み込んでしまい、げっぷが出やすくなるだけでなく、胃内圧の上昇によって胃酸の逆流を招く原因となります。
早食いを改善するためには、ゆっくりよく噛んで食べるのを意識することが大切です。最初は一口で30回以上噛むことを目標に、意識しながら食事をとってみましょう。そのほかにも一口の量を増やす、歯ごたえのある食材を選ぶ、食事の時間に余裕を持つなどの対策も有効です。
腹部を締め付ける服装は避ける
腹部を締め付ける服装は胃酸の逆流を招きやすくなるため、なるべく避けましょう。具体的にはベルトやコルセット、ガードル、着物の帯などが挙げられます。ウエストがゴムになっているズボンやスカートも、ゴムがきつすぎるとお腹を締め付けてしまうため注意が必要です。
腰痛の治療や予防で腰痛ベルト・コルセットを使用しなければいけない場合は、医師に相談の上、使用タイミングや締める強さを調整してみましょう。
寝る2~3時間前までに食事を済ませる
逆流性食道炎を改善するためには、寝る2~3時間前までに食事を済ませることが大切です。
食後すぐに横になってしまうと、胃酸が逆流しやすくなってしまいます。少なくとも食後2~3時間は横にならず、真っ直ぐな姿勢を保つようにしましょう。
生活リズムの関係で早めに寝なければいけない場合は、頭と上半身を高くすることで胃酸が逆流しにくくなるため、試してみてください。
バランスの良い食生活を心がける
逆流性食道炎を改善するためには、バランスの良い食生活を心がけることが大切です。
例えば揚げ物やラーメン、フライドチキン、ピザといった高脂肪・高たんぱくな食事ばかり摂っていると、胃酸の過剰分泌を招いたり、食べ物の消化に時間がかかり胃の負担を増やしたりすることがあります。栄養素が偏ることなく、バランスの良い食事をとるようにしましょう。
またバランスの良い食生活は逆流性食道炎を改善するだけでなく、健康的な体を維持するためにも重要なポイントとなります。
胃酸を増やす食事は控える
逆流性食道炎は胃酸の過剰分泌により起こるため、胃酸を増やす食事は控えましょう。
胃酸の過剰分泌を招く恐れのある食事として、具体的に以下が挙げられます。
- 辛いもの
- 酸っぱいもの
- 甘いもの
- 脂っこいもの
- 塩分の高いもの
- アルコール
- 炭酸飲料
- カフェイン
上記のような食事はなるべく控え、胃に負担のかからない食事を選びましょう。
逆流性食道炎に関するよくある質問

逆流性食道炎に関するよくある質問をまとめました。
- 逆流性食道炎の検査・診断方法は?
- 逆流性食道炎の治療方法は?
- 逆流性食道炎は再発する?
- 逆流性食道炎で夜寝られないときの対処法は?
ここでは上記4つの質問についてそれぞれ解説します。
逆流性食道炎の検査・診断方法は?
逆流性食道炎の検査は、基本的に内視鏡検査が行われます。口または鼻から内視鏡を挿入し、食道や粘膜の状態を直接観察して診断します。
「内視鏡検査は苦しそう」というイメージを持つ方も少なくありませんが、鼻から内視鏡を挿入する『経鼻内視鏡検査』は嘔吐反射が少なく、比較的楽に検査を受けることが可能です。
大沼田メディカルクリニックでは経鼻内視鏡での検査に加え、鎮静剤を使用するため、苦痛を抑えた検査が受けられます。
逆流性食道炎の治療方法は?
逆流性食道炎の主な治療方法は、薬物療法、生活習慣の改善、手術療法の3つです。
基本的には薬物療法で症状をコントロールしながら、生活習慣を改善して完治を目指すことになります。薬物療法では、胃酸の分泌を抑える薬や胃酸を中和する薬、食道の粘膜を保護する薬、消化管ぜん動運動促進薬などが処方されることが多いです。
また生活習慣の改善では、栄養バランスの整った食事をとること、肥満を改善し適正体重を維持すること、早食いや食べすぎを改善することなどが大切になります。
胃に負担のかかる生活習慣や食生活を改善することで、逆流性食道炎の根本的な治療につながります。
逆流性食道炎は再発する?
逆流性食道炎は、完治しても再発することがあります。これは下部食道括約筋に異常が生じたり、生活習慣が乱れてしまったりすることが主な原因です。
逆流性食道炎の再発自体は珍しいことではありません。症状が改善されたからといって薬の服用をやめたり、元の生活習慣に戻したりしてしまうと、再発することがあります。
逆流性食道炎の再発を防ぐためには、症状が改善してきてからも医師の指示通りに服薬を続け、規則正しい生活習慣を維持することが大切です。
逆流性食道炎で夜寝られないときの対処法は?
逆流性食道炎で夜寝られないときは、体の左側を下にして寝たり頭と上半身を高くしたりして、楽な姿勢で寝るようにしましょう。
またより良い睡眠をとるためには、心身ともにリラックスすることも大切なため、以下の方法も試してみてください。
- 寝る前にスマホやパソコンの画面を見ない
- 本を読んで心を落ち着かせる
- 軽いストレッチをする
リラックスすることで自律神経への負担を和らげ、胃酸の逆流を防ぐことにもつながります。
まとめ
逆流性食道炎は寝ているときに胃酸が逆流しやすくなるため、寝ているときの姿勢に注意が必要です。今回紹介したように、体の左側を下にして寝る・頭と上半身を高くする・お腹を圧迫しない服装や姿勢で寝るなどのポイントを取り入れてみてください。
またこれらの対策は一時的に症状を和らげるためのもので、逆流性食道炎の根本的な治療には至りません。そのため夜寝られないほどの症状にお悩みの方は、病院で適切な検査と治療を受けることが大切です。
『大沼田メディカルクリニック』では、患者さんの負担が少ない経鼻内視鏡検査に対応しています。口から内視鏡を挿入するよりも苦痛が少ないため、胃酸の逆流による症状にお悩みの方はぜひ当院までご相談ください。
人気記事
カテゴリー
このコラムについて
当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。
現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ご予約・お問い合わせ
常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。
8:30〜12:30 / 15:30〜19:00
休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日