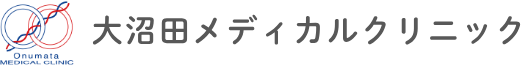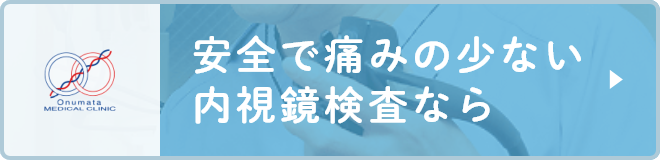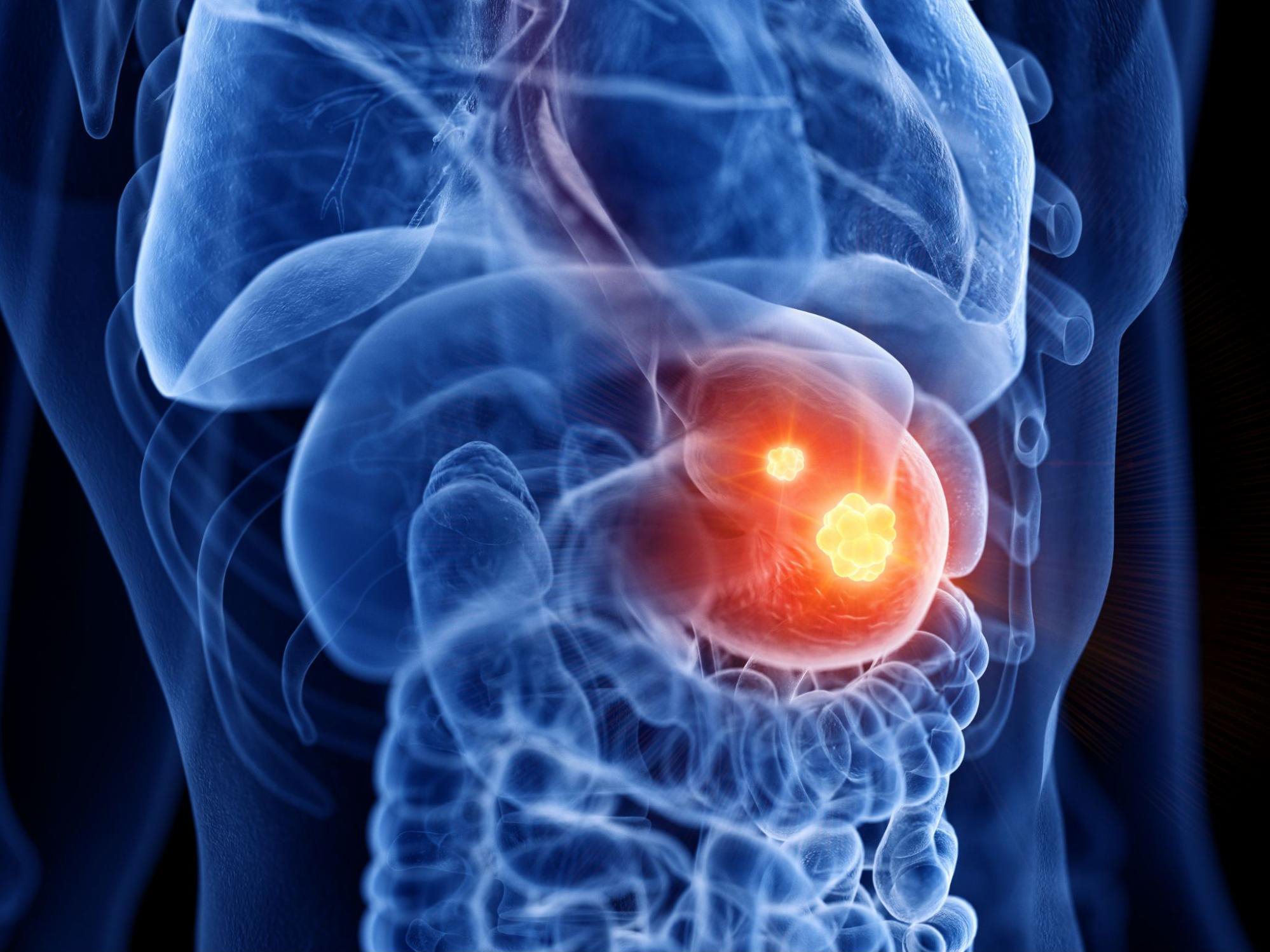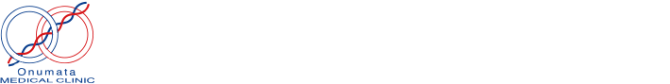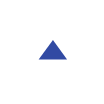逆流性食道炎はストレスが関係している?考えられる原因や治療方法について解説

目次
逆流性食道炎は胃酸が食道に逆流し、食道粘膜で炎症が起こる病気です。胃酸の分泌は自律神経でコントロールされているため、ストレスをため込むと自律神経が乱れ、胃酸が過剰分泌されることで逆流性食道炎を引き起こすことがあります。
この記事では、逆流性食道炎とストレスの関係性について詳しく解説します。逆流性食道炎の原因や検査・診断方法、治療方法、よくある質問などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
逆流性食道炎とは

逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が何らかの原因によって逆流することにより、食道粘膜で炎症が起こる病気です。
主な症状は胸やけや呑酸(酸っぱい胃液が口まで上がってくること)、喉の違和感、喉・胸が詰まるような閉塞感、胸痛、咳などです。
胃酸や胃の内容物が逆流する原因はさまざまで、ストレスや加齢、食習慣、肥満、姿勢などがあります。食道と胃の境目にある下部食道括約筋の緩みも、逆流性食道炎を発症する原因の一つです。
下部食道括約筋は、胃の内容物が食道に逆流しないようにバルブのような役割を果たしているため、この筋肉が緩むと逆流しやすくなります。
逆流性食道炎とストレスの関係性

逆流性食道炎とストレスには深い関係があります。なぜなら胃酸の逆流を起こす原因となる胃酸の分泌は、自律神経によってコントロールされているためです。
つまり自律神経が乱れると胃酸の分泌量やタイミングが変化し、胃酸の過剰分泌につながることがあるのです。
自律神経の乱れを引き起こす原因は、ストレスも含めて以下が挙げられます。
- 精神的ストレス(人間関係や仕事関係のプレッシャー、環境の変化など)
- 身体的ストレス(過労や怪我など)
- 睡眠不足
- 不規則な食生活
- 更年期障害など
また精神的・身体的ストレスは自律神経を乱すだけでなく、うつ病や自律神経失調症、適応障害、摂食障害などさまざまな病気の原因にもなります。
逆流性食道炎だけでなく、上記のような病気を予防するためにも、自分なりのストレス解消方法を見つけておくことが大切です。
ストレス以外で考えられる逆流性食道炎の原因

ストレス以外で考えられる逆流性食道炎の原因として、以下が挙げられます。
- 早食い・食べ過ぎ
- 高脂肪・高たんぱくな食事
- 加齢
- 肥満・姿勢の悪さ
- 喫煙
- 薬の服用
ここでは上記6つの原因についてそれぞれ解説します。
早食い・食べ過ぎ
逆流性食道炎を引き起こす原因の一つとして、早食いや食べすぎが挙げられます。どちらも胃酸の過剰分泌を引き起こし、逆流の原因となります。
胃に大量に食べ物が入り込んでくると胃が下に引き伸ばされ、それによって下部食道括約筋が緩んでしまうのも原因の一つです。
早食いの習慣がある方やよく食べ過ぎてしまう方は、食事量や飲み込むペースを改善しましょう。食べ過ぎは食事量を減らすだけで良いですが、早食いを改善するためには、普段の食生活の癖から見直す必要があります。
一口ずつよく噛んでから飲み込むことを意識する、一口あたりの量を減らす、時々箸をおくようにするなどの対策が有効です。
高脂肪・高たんぱくな食事
逆流性食道炎を引き起こす原因として、高脂肪・高たんぱくな食事が挙げられます。高脂肪・高たんぱくな食事は消化に悪く、胃酸の分泌量が過剰になってしまいがちです。胃酸分泌量が増えると自然と逆流のリスクも高まるため、逆流性食道炎を引き起こす原因になり得ます。
このリスクを避けるためには、胃への負担が少なく消化に良い食事をとることが大切です。
| 消化に良い食事 | 消化に悪い食事 | |
|---|---|---|
| 主食 | ごはん、おかゆ、うどん、パンなど | 玄米、スパゲティ、ラーメン、焼きそばなど |
| 主菜 | 脂身の少ない肉、白身魚、卵料理、卵豆腐、納豆、豆腐 | 脂身の多い肉、脂身の多い魚、イカ、タコ、貝類 |
| 副菜 | キャベツ、ほうれん草、小松菜、白菜、大根、かぶ、人参、じゃがいも、里芋など | ごぼう、たけのこ、コーン、山菜、きのこ、さつまいもなど |
| 果物 | りんご、バナナ、桃、メロン、果物缶など | パイナップル、梨、柿、ドライフルーツなど |
上記を参考に、胃にやさしく消化しやすい食品を積極的に選びましょう。
加齢
逆流性食道炎を引き起こす下部食道括約筋の緩みは、加齢に伴う筋力低下により起こることがあります。
また、下部食道括約筋だけでなく、ぜん動運動も加齢の影響を受けます。ぜん動運動は食べたものを移動するための筋肉の収縮のことで、加齢に伴ってこの動きが弱くなると、胃の内容物が滞在する時間が長くなるのです。そうすると胃もたれや胃痛といった胃の不快な症状が現れやすくなります。
肥満・姿勢の悪さ
肥満や姿勢の悪さも、逆流性食道炎を引き起こす原因となります。
猫背や前かがみの姿勢を続けていると腹圧が上昇するため、胃酸が逆流しやすくなってしまうのです。さらにコルセットやガードル、ベルト、着物の帯などの直接お腹を締め付けるものも、胃酸の逆流を招く原因となります。
肥満体型の方は痩せる、姿勢が悪い方は普段から姿勢を意識して生活する、なるべくお腹を締め付けるようなものは身につけないなどに注意して過ごすようにしましょう。
また猫背姿勢は筋力低下が原因となっていることもあるため、姿勢を意識するだけでなく、ストレッチや筋力トレーニングなども取り入れてみてください。
喫煙
逆流性食道炎を引き起こす原因として、喫煙も挙げられます。喫煙には胃酸の分泌を促進する作用や下部食道括約筋を緩める作用があるため、胃酸の逆流を招く原因になる場合があります。
さらにタバコに含まれる有害物質によって粘膜で炎症が起こりやすくなるため、逆流性食道炎の症状がある方は禁煙を検討しましょう。
喫煙は逆流性食道炎だけでなく、咽頭がんや食道がん、胃がんなどの発症リスクを高める恐れがあるため、症状のない方も禁煙を推奨します。
自力での禁煙が難しい場合は、医療の力で禁煙をサポートする『禁煙外来』の受診も検討してみてください。
薬の副作用
薬の副作用によって逆流性食道炎を発症する場合もあります。
具体的にはカルシウム拮抗剤系の血圧降圧剤や喘息・心臓疾患で服用する薬などが該当し、これらの薬は副作用として、下部食道括約筋を緩める恐れがあります。下部食道括約筋が緩むと胃酸が逆流しやすくなり、逆流性食道炎が起こるのです。
副作用で起こる症状は一時的なものですが、不安な方は医師に相談しておくとよいでしょう。
逆流性食道炎の検査・診断方法

逆流性食道炎の検査方法は、基本的に内視鏡検査となります。
口または鼻から内視鏡を挿入し、上部消化管の状態を直接観察することで、粘膜の状態から症状の重症度を判定することが可能です。
逆流性食道炎は粘膜の状態によって以下の6つのグレードに分類されます。
| グレードN | 変化が特に認められない |
| グレードM | 粘膜に赤みがみられる |
| グレードA | 直径5ミリ未満の粘膜の炎症があり、皮膚のひだの一部に炎症がみられる |
| グレードB | 直径5ミリ未満の粘膜の炎症があり、他の粘膜のヒダの炎症と連続していない |
| グレードC | 連続した粘膜のヒダの炎症がみられる |
| グレードD | 全周75%以上の粘膜に炎症がみられる |
グレードNが正常な状態で、グレードMが一番症状が軽く、A、B、C、Dと進むにつれて重症度が高まっていきます。
逆流性食道炎の治療方法

逆流性食道炎の治療方法は3つあります。
- 生活習慣の改善
- 薬物療法
- 手術療法
ここでは上記3つの治療方法についてそれぞれ解説します。
生活習慣の改善
逆流性食道炎は主に生活習慣が原因で引き起こされるため、日々の生活習慣の見直しが必要となります。
具体的には以下の通りです。
- 食生活の改善
- 脂肪分やたんぱく質の摂取量に注意する
- 消化に良い食事を摂取する
- 食べ過ぎや早食いを控える
- 刺激物・酸味の強いもの・甘いものは控える
- 嗜好品を控える
- 飲酒・喫煙・カフェインの摂取を控える
- 腹圧の上昇に注意する
- 肥満を改善する
- 猫背や前かがみの姿勢を改善する
- ベルトやコルセットなどのお腹を締め付ける物を身につけない
薬物療法
逆流性食道炎の薬物療法では、基本的に胃酸の分泌を抑える薬が処方されます。患者さんの症状によっては、食道や胃の機能を整える薬、食道の粘膜を保護する薬などが処方される場合もあります。
正しい用法・用量を守って薬を服用するのはもちろんのこと、服用期間中も健康的な生活習慣を意識することが大切です。
手術療法
生活習慣の改善や薬物療法では効果が得られない場合は、手術療法による逆流性食道炎の治療を行う場合があります。
主な手術方法として、『噴門形成術』という外科手術方法が挙げられます。この手術は食道と胃のつなぎ目を締めなおすことで、胃から食道への逆流を抑える治療方法です。特に大きな食道裂孔ヘルニアを患っている患者さんや、薬物療法を避けたい患者さんに適応する場合が多いです。
以前は開腹手術が一般的でしたが、最近は腹腔鏡を用いた手術により、短い入院期間でかつ体への負担を抑えて治療を行えるようになってきています。
逆流性食道炎に関するよくある質問

逆流性食道炎に関するよくある質問をまとめました。
- 逆流性食道炎でやってはいけないことは?
- 逆流性食道炎は自然に治る?
- 逆流性食道炎を放置すると食道がんになる?
ここでは上記3つの質問についてそれぞれ解説します。
逆流性食道炎でやってはいけないことは?
逆流性食道炎でやってはいけないこととして、以下が挙げられます。
- 脂っこい食事ばかりとる
- 刺激の強い食事(辛いもの、酸味の強いものなど)の過剰摂取
- 飲酒・喫煙
- カフェインの過剰摂取
- 食後すぐに横になる
- 早食い・食べ過ぎ
- ベルトやコルセットなどのお腹を締め付ける衣服の着用
- ストレスをため込む
逆流性食道炎を早く治すためには、胃にやさしい食生活を心がけることが大切です。
またストレスをため込むのも胃酸の過剰分泌につながるため、リラックスできる環境を整えましょう。
逆流性食道炎は自然に治る?
逆流性食道炎が自然に治るかどうかは、症状の程度や原因によって異なります。
軽度の場合は、生活習慣の改善によって症状が軽減し、完治することもあります。しかし慢性化している場合や、症状が頻繁に現れる場合は、医師の診察を受けることが大切です。
特に強い胸やけや呑酸が続く場合は、医療機関で診断を受けるようにしましょう。
逆流性食道炎を放置すると食道がんになる?
逆流性食道炎を長期間放置すると、食道がんのリスクが高まる可能性があります。
特に逆流を繰り返すことで食道の粘膜が炎症を起こし、バレット食道と呼ばれる状態になると、特殊な食道がんの発症リスクが上昇します。
逆流性食道炎を持っているすべての人が必ず食道がんになるわけではありませんが、長期間症状を放置したり、治療せずに悪化させたりすると、がんのリスクが増すため注意が必要です。
食道がんを予防するためには、早期診断と適切な治療を受けることが大切になります。
まとめ
逆流性食道炎とストレスは密接に関係しており、ストレスをため込むことで自律神経が乱れ、胃酸の逆流が起こることがあります。
また逆流性食道炎はストレスだけでなく、早食いや食べ過ぎ、高脂肪・高たんぱくな食事、加齢、肥満、姿勢の悪さ、喫煙、薬の副作用などさまざまな原因によって引き起こされます。
特に生活習慣が原因となるケースが多いため、食生活が乱れがちな方は注意が必要です。
『大沼田メディカルクリニック』では、内視鏡検査による病気の早期発見が可能です。気になる症状がある方はもちろん、健康状態を確認したい方もぜひ当院までご相談ください。
人気記事
カテゴリー
このコラムについて
当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。
現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ご予約・お問い合わせ
常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。
8:30〜12:30 / 15:30〜19:00
休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日