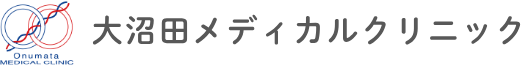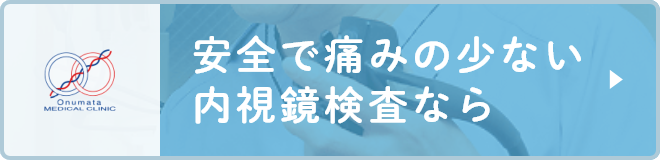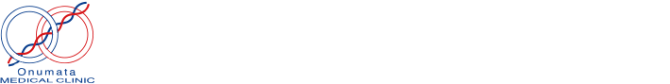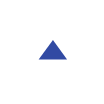逆流性食道炎になりやすい食事とは?食生活や生活習慣のポイントを解説
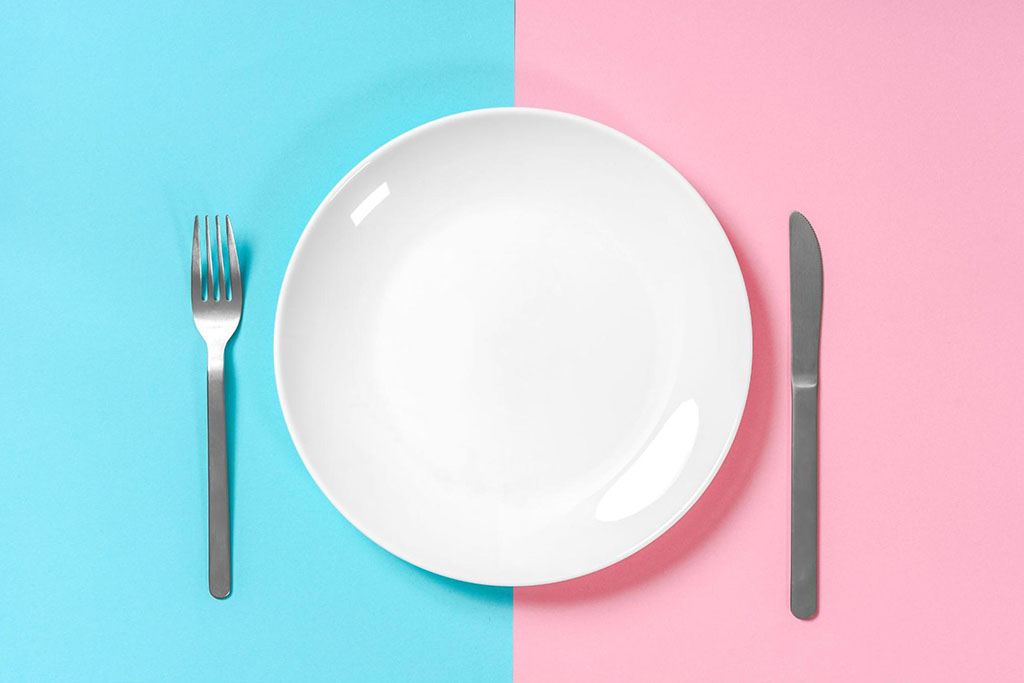
逆流性食道炎は、胃酸が食道へと逆流することによって、食道粘膜で炎症が起こる病気です。さまざまな原因によって引き起こされる病気ですが、食事による影響が大きいため、日々の食生活に注意を払うことが大切です。
この記事では、逆流性食道炎になりやすい人の食事の特徴について詳しく解説します。逆流性食道炎の食事のポイントやおすすめのコンビニ食事メニュー、食事以外のポイントなどもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
逆流性食道炎とは

逆流性食道炎とは、胃酸が食道へ逆流し、食道粘膜に炎症を引き起こす病気です。
食道と胃の境目には下部食道括約筋と呼ばれる筋肉があり、本来であればこれが胃酸の逆流を防いでいます。しかし何らかの要因によってこの筋肉が緩んだり、圧力が低下したりすると、胃酸が食道に逆流しやすくなり、食道粘膜が刺激されて炎症が生じてしまうのです。
ここでは逆流性食道炎の症状や主な原因について解説します。
逆流性食道炎の症状
逆流性食道炎の代表的な症状として、胸やけや呑酸(酸っぱい液体が口の中に上がってくる感じ)が挙げられます。
胸やけは特に食後や横になったときに感じやすく、胃酸が食道を刺激することで起こります。胸やけがひどくなると、夜中に目が覚めたり心臓の病気と同じような胸の痛みを感じたりする場合も少なくありません。
また逆流した胃酸が喉や気管にまで達すると、慢性的な咳や喉の違和感、声がれの原因になることもあります。
逆流性食道炎の症状は人によって異なり、軽度の症状から重度の痛みを伴うものまでさまざまです。特に長期間放置すると、食道粘膜の損傷が進み慢性的な炎症を引き起こす可能性があるため、症状が続く場合は早めに医療機関を受診することをおすすめします。
逆流性食道炎の主な原因
逆流性食道炎の主な原因は、胃酸の過剰分泌と下部食道括約筋の機能低下です。
これらを引き起こす要因として、以下が挙げられます。
- 脂肪分の多い食事
- 食べすぎ・飲みすぎ
- 刺激の強い食品(辛いもの、酸っぱいもの、アルコール、カフェインなど)の過剰摂取
- 生活習慣(就寝前の食事や食後すぐに横になる習慣など)
- ストレス
- 肥満
- 猫背
- 喫煙
- 加齢に伴う筋力低下
これらの原因が重なることで逆流性食道炎が発症しやすくなるため、食生活の見直しや生活習慣の改善が予防と治療において重要なポイントとなります。
逆流性食道炎になりやすい人の食事の特徴

逆流性食道炎になりやすい人の食事の特徴として、以下が挙げられます。
- 脂っこいものを好んで食べる
- コーヒー・炭酸飲料・アルコールをよく飲む
- 早食いや食べすぎの習慣がある
- 食べてすぐに寝る習慣がある
ここでは上記4つの特徴についてそれぞれ解説します。
脂っこいものを好んで食べる
脂っこいものを好んで食べる人は、逆流性食道炎になりやすいため注意が必要です。
具体的には天ぷらや唐揚げ、フライドポテトなどの揚げ物系、ハンバーガーやピザなどのファストフード系のメニューが挙げられます。
上記のような脂っこいものを食べすぎると、コレシストキニンというホルモンが十二指腸から分泌され、げっぷや胸やけの原因となります。
コーヒー・炭酸飲料・アルコールをよく飲む
コーヒー・炭酸飲料・アルコールをよく飲む人も、逆流性食道炎になりやすい傾向にあります。
コーヒーなどに含まれるカフェインを過剰に摂取すると、下部食道括約筋を緩めたり、胃酸を増やしたりすることがあります。コーヒーに限らず、緑茶や紅茶、コーラなどの飲み物にも注意が必要です。
炭酸飲料は胃を膨張させて内圧を上昇させる恐れがあり、さらにアルコールもコーヒーと同様に、下部食道括約筋を緩める可能性があります。
早食いや食べすぎの習慣がある
逆流性食道炎になりやすい人の食事の特徴として、早食いや食べすぎの習慣があることが挙げられます。
早食いは、食べ物をよく噛まずに飲み込んでしまう影響で空気も一緒に飲み込みやすくなり、げっぷの原因となることがあります。
食べてすぐに寝る習慣がある
食後すぐに横になると、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。
特に胃の内容物が多い状態で寝ると、重力の影響で胃酸が食道へ押し戻され、胸やけや不快感を引き起こしやすくなります。
逆流性食道炎の食事のポイント

逆流性食道炎の食事のポイントは以下の通りです。
- アルカリ性の食品を積極的に摂取する
- 水分豊富な食事を取り入れる
- 消化に良い食事を選ぶ
- アルコール・カフェイン・炭酸飲料は控える
- 胃酸の過剰分泌を抑える食べ物を積極的に摂る
- 胃酸の分泌を促す食事は控える
- 一度に摂る食事量は腹八分目を心がける
- ゆっくりと時間をかけて食べる
- 食後2~3時間以上あけてから寝る
ここでは上記9つのポイントについてそれぞれ解説します。
アルカリ性の食品を積極的に摂取する
アルカリ性の食品は、胃酸を中和し、逆流性食道炎の症状を和らげる効果が期待できます。
例えば、野菜類(ほうれん草、ブロッコリー)、豆類、バナナなどは胃酸の刺激を抑えるのに役立ちます。
これらの食品を積極的に取り入れ、胃酸の過剰な分泌を防ぐことが大切です。
水分豊富な食事を取り入れる
水分豊富な食事は、胃酸の濃度を薄めるだけでなく、食道や胃の粘膜を保護する働きがあります。
スープや味噌汁、おかゆなどは消化にも優しく、胃への負担を軽減できます。特に温かいスープは胃を刺激せず、消化を助けるため、積極的に食事に取り入れるのがおすすめです。
ただし刺激の強い香辛料や塩分の多いスープは逆効果になるため、薄味を心がけましょう。
消化に良い食事を選ぶ
逆流性食道炎の症状を悪化させないためには、胃にやさしい食事を選ぶことが重要です。
脂肪分の多い食事や揚げ物は消化に時間がかかり、胃酸の分泌を促進するため避けるべきです。代わりに白身魚や豆腐、温野菜、うどんなど、消化しやすい食品を取り入れると良いでしょう。
また食材は柔らかく調理し、よく噛んでゆっくり食べることで、胃への負担をさらに軽減できます。
アルコール・カフェイン・炭酸飲料は控える
アルコールやカフェイン、炭酸飲料は胃酸の分泌を促進し、食道の下部括約筋を緩めるため、逆流性食道炎を悪化させる原因になります。
特にビールや炭酸飲料は胃を膨らませ、胃酸の逆流を引き起こしやすくなります。
また日頃からコーヒーや紅茶をよく飲んでいる場合は、カフェインを含まないハーブティーや白湯を選ぶのがおすすめです。
これらの飲み物を控えることで、胃の負担を軽減し、症状の改善につながります。
胃酸の過剰分泌を抑える食べ物を積極的に摂る
逆流性食道炎の食事では、胃酸の過剰分泌を抑える食べ物を積極的に摂りましょう。
例えばキャベツには胃酸の過剰な分泌を抑えるビタミンUという物質が含まれています。
この物質はレタスやアスパラガス、ブロッコリーなどにも含まれているため、積極的に摂ると良いでしょう。
胃酸の分泌を促す食事は控える
胃酸の分泌を促す食品を過剰に摂取すると、逆流性食道炎の症状が悪化する可能性があります。
脂っこい食事や揚げ物、辛いもの、酸味の強い食品(柑橘類や酢)などは特に注意が必要です。またチョコレートやケーキなどの甘い食べ物もなるべく控えた方が良いでしょう。
一度に摂る食事量は腹八分目を心がける
食べ過ぎは胃の膨張を招き、胃酸の逆流を引き起こしやすくなります。
特に満腹まで食べると胃の圧力が高まり、食道へ胃酸が押し上げられる原因になります。これを防ぐためには、腹八分目を意識し、少量ずつ食べることが大切です。
1回の食事量を減らして回数を増やすことで、胃への負担を軽減し、逆流を防ぎやすくなります。
ゆっくりと時間をかけて食べる
早食いは食べ物を十分に噛まずに飲み込むため、胃に負担をかけ、胃酸の分泌を促す原因となります。また大きな食べ物の塊が胃に入ると、消化に時間がかかり、胃の働きを悪化させることもあります。
これを防ぐために、一口ずつよく噛み、時間をかけて食べることが大切です。
食後2~3時間以上あけてから寝る
食後すぐに横になると、胃酸が食道に逆流しやすくなります。
特に夕食後にすぐ就寝すると、胃の消化が追いつかず、逆流性食道炎の症状が悪化するリスクが高まります。そのため、食後2~3時間は体を起こした状態を保ち、消化が進むのを待つことが大切です。
どうしても横になりたい場合は、上半身を少し高くするなど、胃酸の逆流を防ぐ工夫をすると良いでしょう。
コンビニで買える逆流性食道炎のときにおすすめの食事メニュー

逆流性食道炎の症状があるときは、胃酸の分泌を抑え、消化にやさしい食事を選ぶことが大切です。
コンビニで買える逆流性食道炎のときにおすすめの食事メニューとして、以下が挙げられます。
- レトルトのおかゆ
- コンビニおでん
- 豆腐など
上記のような食事なら薄味で消化に良く、調理の手間もかかりません。
逆流性食道炎の食事以外のポイント

逆流性食道炎の食事以外のポイントは以下の通りです。
- 胃を圧迫する姿勢は避ける
- お腹を締め付けるものを身につけない
- 腹式呼吸を行う
- 禁煙をする
ここでは上記4つのポイントについてそれぞれ解説します。
胃を圧迫する姿勢は避ける
逆流性食道炎では、胃を圧迫する姿勢は避けることが大切です。猫背や前かがみの姿勢は胃を圧迫し、胃酸が逆流しやすくなってしまいます。
特にデスクワークをする方は、自分が意識していない間に猫背や前かがみの姿勢になっていることがあるため、姿勢を正すことを意識してみましょう。
また寝るときの姿勢にも注意が必要です。逆流性食道炎は寝ているときに胃酸の逆流が起こりやすくなるため、なるべく上半身を高くして寝ましょう。
例えば背中に積み重ねたタオルを置くことで、上半身に傾斜をつけられるため、寝ている間の胃酸の逆流を防ぎやすくなります。
お腹を締め付けるものを身につけない
逆流性食道炎の食事以外のポイントとして、お腹を締め付けるものを身につけないことが挙げられます。
具体的にベルトやコルセット、ガードル、着物の帯などはなるべく控えることをおすすめします。
腹式呼吸を行う
逆流性食道炎を発症したら、腹式呼吸を行う癖をつけることをおすすめします。
胃と食道のつなぎ目の位置がずれることにより生じる『食道裂孔ヘルニア(胃酸が逆流する原因の一つ)』を直接治すためには手術療法しかありません。
しかし腹式呼吸を継続することで横隔膜が鍛えられるため、胃と食道の緩みを改善し、結果として逆流性食道炎の症状改善につながります。
禁煙をする
タバコに含まれるニコチンは下部食道括約筋圧を低下させる恐れがあるため、逆流性食道炎を発症したらなるべく禁煙するのが望ましいです。
禁煙するときのポイントは以下の通りです。
- 禁煙開始日を決める
- 吸いたい気持ちになったときの対処法(洗顔・歯磨き・深呼吸など)を練習する
- 禁煙治療用アプリを活用する
- 禁煙補助薬を使用する
また自力での禁煙が難しく感じる場合は、医療の力で禁煙を目指す『禁煙外来』を受診するのもおすすめです。
まとめ
逆流性食道炎を発症しやすい人の食事の特徴として、脂っこいものを好んで食べること、コーヒー・炭酸飲料・アルコールを過剰摂取すること、早食いや食べすぎの習慣があることなどが挙げられます。
逆流性食道炎では、胃にやさしく負担のかからない食事を意識することが大切です。具体的にはアルカリ性の食事や水分豊富な食事、消化に良い食事、胃酸の過剰分泌を抑える食事などを積極的に摂ることをおすすめします。
『大沼田メディカルクリニック』では、経鼻内視鏡検査に対応しています。逆流性食道炎はもちろん、そのほかの消化管疾患がないか確認することも可能です。
胃酸の逆流や胸やけなどの症状にお悩みの方は、ぜひ当院までご相談ください。
人気記事
カテゴリー
このコラムについて
当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。
現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ご予約・お問い合わせ
常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。
8:30〜12:30 / 15:30〜19:00
休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日