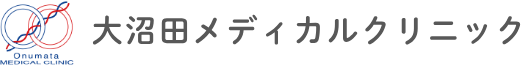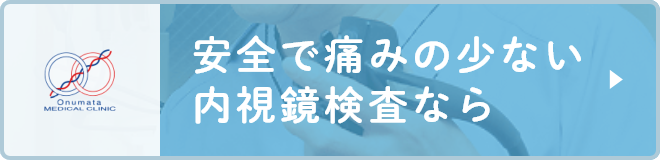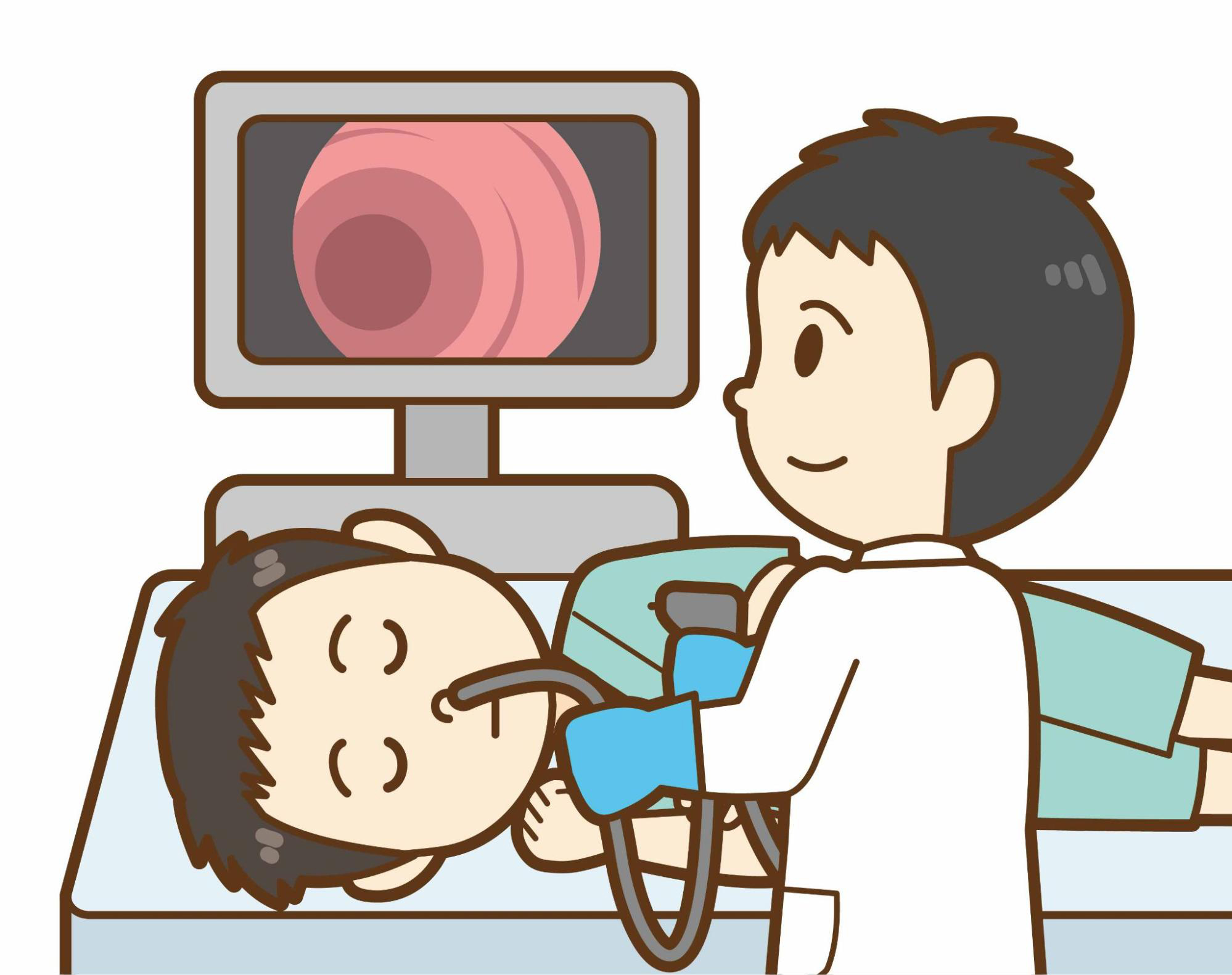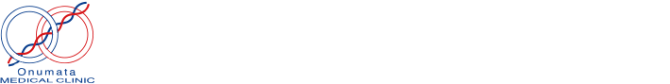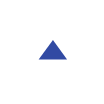機能性ディスペプシアの原因は?症状・検査方法・治療方法も解説

目次
機能性ディスペプシアとは、胃痛や胃もたれといった不快な症状が現れているにもかかわらず、検査で異常が認められない病気です。胃の運動障害や胃・十二指腸の知覚過敏、生活習慣などさまざまな要因によって引き起こされます。
この記事では、機能性ディスペプシアの原因について詳しく解説します。機能性ディスペプシアの主な症状やセルフチェックリスト、検査方法、治療方法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
機能性ディスペプシアとは

機能性ディスペプシアとは、胃の痛みや胃もたれといった消化器症状に悩んでいるにもかかわらず、内視鏡検査を受けても、胃潰瘍や胃がんといった明確な異常が見当たらない病気です。
英語表記の『functional dyspepsia』の頭文字を取って、FDと呼ばれることもあります。
ディスペプシアは元々『消化不良』や『胃の不快感』を意味するギリシャ語が語源となっており、主な症状として以下のようなものが挙げられます。
- みぞおち辺りの痛み
- みぞおちに焼けるような感覚がある
- 食後に胃もたれする
- 少し食べただけでお腹がいっぱいになるなど
上記のような症状があるにもかかわらず、胃や食道、十二指腸などに炎症や潰瘍などが見当たらなければ、機能性ディスペプシアと診断されます。
機能性ディスペプシアの主な原因

機能性ディスペプシアの主な原因として、以下が挙げられます。
- 胃の運動障害
- 胃・十二指腸の知覚過敏
- ストレスや過労
- 生活習慣
- 胃酸の過剰分泌
- ピロリ菌感染
- 体質的な要因
ここでは上記7つの原因についてそれぞれ解説します。
胃の運動障害
機能性ディスペプシアの主な原因の一つとして、胃の運動障害が挙げられます。
胃には『胃排出』と『胃適応性弛緩』という2つの機能がありますが、このいずれかで障害が起きていると胃の不快な症状を招くことがあるのです。
胃排出は胃から十二指腸まで食べ物が移動することを指し、胃適応性弛緩は食道から入ってきた食べ物を胃に貯めて消化するための機能を指します。
胃適応性弛緩に障害が起きていると、食事を始めてすぐにお腹がいっぱいになったり吐き気を催してしまったりすることがあります。また胃排出に障害が起こると、消化が終わってもなかなか食べ物が移動せず、胃もたれが生じる原因にもなるのです。
このような胃の障害は、自律神経の失調とも関連性があるとされています。
胃・十二指腸の知覚過敏
機能性ディスペプシアの原因の一つとして、胃・十二指腸の知覚過敏が挙げられます。胃や十二指腸が、少ない刺激で症状が引き起こされやすくなっている状態です。
この状態で少量の食べ物が胃に入ると、満腹感や胃痛、胃もたれ、吐き気などの症状が現れるようになります。
ストレスや過労
ストレスや過労も機能性ディスペプシアの原因の一つです。
胃や腸といった消化管は脳と密接に連携しながら働いているため、情報のコントロールを行う自律神経を通して影響を受けることがあります。
ストレスや過労などにより自律神経が乱れると、胃や食道の動きが悪化し、さまざまな消化器症状を起こす原因となるのです。精神的・肉体的ストレスを感じやすい環境にいる方は、自律神経が乱れやすくなるため注意が必要です。
生活習慣
機能性ディスペプシアを引き起こす原因として、生活習慣も挙げられます。
具体的には以下のようなものです。
- 暴飲暴食
- 高脂質の食事
- 刺激の強い飲食物の過剰摂取
- カフェインの過剰摂取
- 飲酒や喫煙
- 睡眠不足
- 不規則な生活
特に不規則な睡眠や食事は自律神経を乱す原因となります。
睡眠時間が短い方や暴飲暴食をしてしまう方、栄養バランスの偏った食事ばかり摂っている方などは特に注意が必要です。
胃酸の過剰分泌
胃酸の過剰分泌によって、胃や十二指腸の粘膜が刺激されると、胃痛や胃もたれなどの症状が引き起こされることがあります。
胃酸の過剰分泌が起こる主な原因として、ストレスによる自律神経の乱れ、アルコールや刺激物の摂取、食べすぎ・飲みすぎなどが挙げられます。胃酸の分泌量は自律神経によりコントロールされているため、ストレスをため込まないことや過剰なアルコール・刺激物の摂取を控えることが大切です。
また胃酸の過剰分泌は長期的に続くと胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因にもなり得るため、なるべく早めに改善しましょう。
ピロリ菌感染
ピロリ菌に感染すると機能性ディスペプシアを引き起こすことがあります。
ピロリ菌は胃粘膜に住み着く細菌の一種で、胃壁や胃粘膜を傷つけながら移動します。ピロリ菌の感染期間が長期にわたると、胃粘膜で炎症が起き、胃の防御機能や運動機能の低下を引き起こすことがあるのです。胃もたれや胃痛といった症状を引き起こすだけでなく、慢性胃炎や萎縮性胃炎、さらには胃潰瘍、胃がんなどの病気のリスクも高まります。
ピロリ菌感染がある場合、除菌をすることで、機能性ディスペプシアの症状が消失・改善される可能性があります。
体質的な要因
機能性ディスペプシアは、体質的な要因によって引き起こされる場合もあります。
具体的には遺伝的な要因や生育環境、胃の形などが関係しており、同じストレス環境やライフスタイルでも、発症しやすい人とそうでない人がいるのです。
生まれつきの体質的な要因で機能性ディスペプシアを発症しやすい人の場合、胃内細菌叢により形成される胃内環境のコントロールによって、体質を変えていく必要があります。乳酸菌を摂取し続けることで胃内細菌叢の異常が改善され、胃の症状が和らいだという研究報告もあります。
機能性ディスペプシアの主な症状とセルフチェック

機能性ディスペプシアの主な症状は以下の通りです。
- 胃もたれ
- 胸やけ
- 胃やみぞおちの痛み
- 胃の灼熱感
- よくげっぷがでる
- すぐに満腹になる
- 吐き気
上記のほか、倦怠感や肩こり、手足の冷え、背中の痛み、立ちくらみなどがみられる場合もあります。
機能性ディスペプシアの診断基準では、症状によって『心窩部痛症候群(EPS)』と『食後愁訴症候群(PDS)』の2つに分類されます。
- 心窩部痛症候群(EPS)
- 少なくとも週に1日以上、以下のいずれかまたは両方を満たしている
- つらいと感じる胃やみぞおちの痛みがある
- つらいと感じる胃やみぞおちの灼熱感がある
- 食後愁訴症候群(PDS)
- 少なくとも週に3日以上、以下のいずれかまたは両方を満たしている
- つらいと感じる食後の胃もたれ感がある
- つらいと感じる早期満腹感がある
上記に当てはまる場合は、機能性ディスペプシアの可能性が高いです。
もし悩んでいる症状がある方は、自己判断で終わらせずに病院で正確な診断・治療を受けましょう。
機能性ディスペプシアの検査方法

機能性ディスペプシアには主に3つの検査方法があります。
- 内視鏡検査
- ピロリ菌検査
- その他の検査
ここでは上記3つの検査方法についてそれぞれ解説します。
内視鏡検査
機能性ディスペプシアの基本的な検査方法となるのが、内視鏡検査です。
胃痛や胃もたれ、吐き気といった機能性ディスペプシアの主な症状は、さまざまな消化管疾患で起こり得るものです。
そのため内視鏡検査で胃や食道、十二指腸に炎症や潰瘍、がんといった器質的疾患が見当たらないかチェックする必要があります。
さらに感染や炎症状態、内分泌機能などを確認する血液検査や腹部エコー検査などさまざまな検査を行ったうえで、異常が見つからなければ機能性ディスペプシアと診断されるのです。
また内視鏡検査には鼻から内視鏡を挿入する『経鼻内視鏡検査』と口から内視鏡を挿入する『経口内視鏡検査』の2種類あります。
経鼻内視鏡検査は嘔吐反射が起こりづらく、より少ない負担で検査を受けることが可能です。
病院によっては鎮静剤を使用してさらに楽に検査を受けられる場合もあるため、不安な方は検査前に相談してみるとよいでしょう。
ピロリ菌検査
ピロリ菌の感染が機能性ディスペプシアを引き起こすことがあるため、ピロリ菌検査を行う場合があります。
ピロリ菌の検査方法には、内視鏡を使う検査方法と内視鏡を使わない検査方法の2つに分けられます。
具体的な検査方法は以下の通りです。
| 内視鏡を使う検査方法 | 迅速ウレアーゼ試験法 | ピロリ菌が持つ酵素(ウレアーゼ)の活性を利用した検査方法 |
| 鏡検法 | 内視鏡で採取した胃の組織を特殊な薬剤で染色し、顕微鏡で直接ピロリ菌を探す検査方法 | |
| 培養法 | 内視鏡で採取した胃の組織を5~7日間培養し、ピロリ菌の有無を確認する検査方法 | |
| 内視鏡を使わない検査方法 | 尿素呼気試験法 | ピロリ菌のウレアーゼの活性を利用し、呼気中に含まれる二酸化炭素の割合でピロリ菌の有無を調べる方法 |
| 抗体検査法 | 血液中や尿中のピロリ菌の抗体の有無を調べる方法 | |
| 抗原検査法 | 糞便中のピロリ菌の抗原の有無を調べる方法 |
なお、病院によって対応している検査方法は異なります。
その他の検査
その他の検査方法として、血液検査や超音波検査、腹部CT検査などを行う場合があります。血液検査では感染や炎症状態、内分泌機能、全身状態などを確認することが可能です。
これらの検査方法を組み合わせ、異常がみられなければ機能性ディスペプシアと診断されます。
機能性ディスペプシアの治療方法

機能性ディスペプシアの基本的な治療方法として、以下の3つが挙げられます。
- 薬物療法
- 生活習慣の改善
- 食生活の改善
ここでは上記3つの治療方法についてそれぞれ解説します。
薬物療法
機能性ディスペプシアの胃痛や胃もたれといった症状には、薬物療法で対応します。
主に以下のような薬が処方されることが多いです。
- 胃の運動機能が低下している場合:運動機能を改善する薬
- 胃酸の過剰分泌が起きている場合:胃酸の分泌を抑制する薬(ボノプラザン、プロトンポンプ阻害薬、H2ブロッカーなど)
- 精神的症状が強い場合:抗うつ薬や抗不安薬
またピロリ菌に感染している場合は、ピロリ菌除菌治療を行います。ピロリ菌除菌治療では、胃酸の分泌を抑える薬1種類と抗菌薬2種類を1日2回、7日間服用します。ピロリ菌の一回目の除菌治療成功率は75〜90%程度です。
服用終了後、8週間以上経過してから判定試験を行い、除菌が成功しなければ二回目の除菌治療に進むことになります。
生活習慣の改善
機能性ディスペプシアの治療では、生活習慣の改善が必要になる場合があります。
生活習慣を改善するときのポイントは以下の通りです。
- ストレスを解消する方法を見つける
- 疲れをため込まない工夫をする
- 規則正しい睡眠習慣と十分な睡眠時間を確保する
- 適度な運動習慣をつける
- 禁煙する
このほかにもさまざまなポイントがありますが、医師のアドバイスも受けながら改善していくことが大切です。
食生活の改善
機能性ディスペプシアの治療では、食生活の改善も重要になります。食生活の改善におけるポイントは以下の通りです。
- 栄養バランスの整った食事を心がける
- 規則正しい食事時間を意識する
- 暴飲暴食を控える
- よく噛んで食事を摂る
- 食べてすぐに横になったり運動したりするのを避ける
胃の健康を保つためには、胃に負担のかからない食生活を意識することが大切です。
食事の栄養バランスはもちろん、よく噛んで食べる・過度な食べすぎは避けるなどの食べ方にも気を配ることがポイントになります。
まとめ
機能性ディスペプシアの主な原因として、胃の運動障害や胃・十二指腸の知覚過敏、ストレスや過労、生活習慣、胃酸の過剰分泌などが挙げられます。さまざまな要因が複雑に絡み合って発症していることが多いため、日頃の生活習慣や食習慣の見直しも重要です。
また他の病気と区別し、機能性ディスペプシアと診断するためには内視鏡検査が必要不可欠になります。
『大沼田メディカルクリニック』では、負担の少ない経鼻内視鏡検査に対応しています。鎮静剤の点滴によってうとうとと眠っているような状態で検査を受けられるため、気になる症状のある方はぜひ当院までご相談ください。
人気記事
カテゴリー
このコラムについて
当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。
現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ご予約・お問い合わせ
常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。
8:30〜12:30 / 15:30〜19:00
休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日