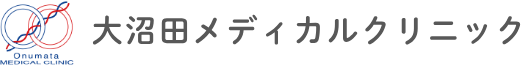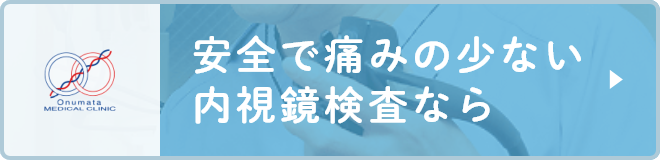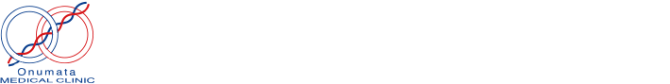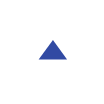胃潰瘍のステージ別の症状とは?原因・検査・治療方法についても解説

目次
胃潰瘍は胃粘膜や胃壁が深く傷つき、みぞおち辺りの痛みや吐き気などの症状が現れる病気です。胃潰瘍は症状の進行度別にステージがあり、悪化すると胃壁に穴が開いてしまい、緊急手術が必要になるケースもあります。
この記事では、胃潰瘍のステージ別の症状について詳しく解説します。胃潰瘍の原因や検査方法、治療方法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
胃潰瘍とは

胃潰瘍は何らかの原因によって胃の粘膜が傷つけられ、その損傷が胃壁の筋層にまで至っている状態です。
胃潰瘍には急性胃潰瘍と慢性胃潰瘍の2種類あり、それぞれ以下のような特徴があります。
- 急性胃潰瘍:浅い不整形の潰瘍やびらんが多発する
- 慢性胃潰瘍:円形の潰瘍やびらんが多発する
びらんは粘膜表面が欠損した状態で、潰瘍はより深い層まで欠損した状態です。胃潰瘍には良性と悪性があり、良性胃潰瘍の場合は通常の治療で完治を目指せます。一方、悪性胃潰瘍は胃がんと認められるため、がん治療が必要となります。
胃潰瘍の発症原因は後ほど詳しく解説しますが、ピロリ菌感染やストレス、非ステロイド性抗炎症薬などにより発症することが多いです。炎症が長引くと深刻な病気を引き起こす可能性もあるため、胃潰瘍が疑われるような症状がある場合はすぐに医療機関を受診することをおすすめします。
胃潰瘍のステージ別症状
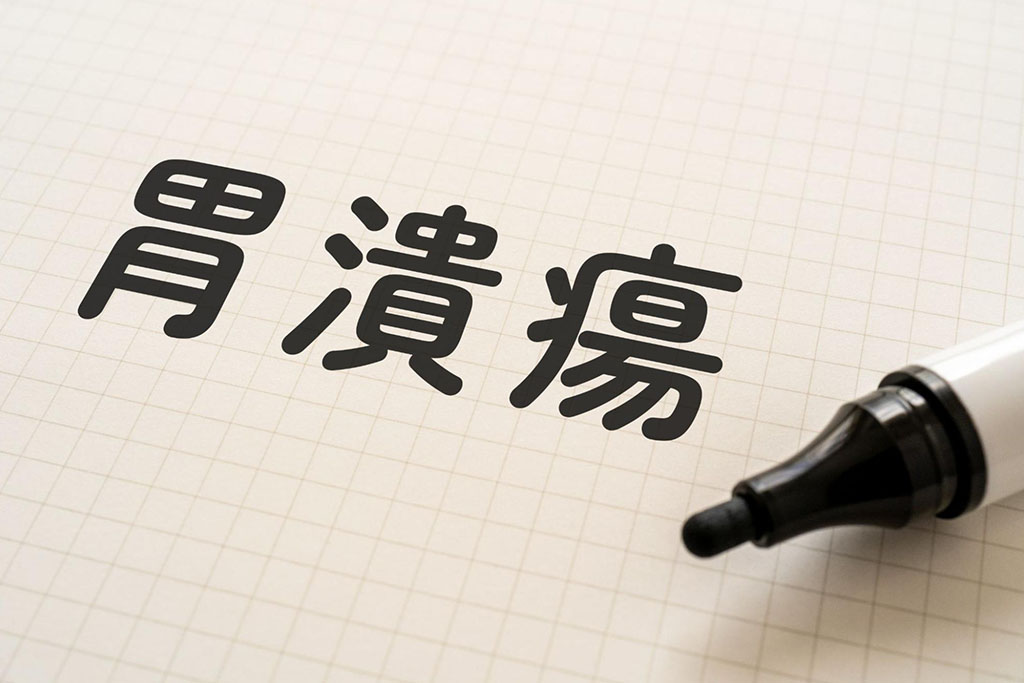
胃潰瘍には大きく分けて、活動期(active stage)、治癒過程期(healing stage)、瘢痕期(scarring stage)の3つのステージがあります。
それぞれのステージをさらに2段階に分けて計6つのステージが存在します。
- A1ステージ
- A2ステージ
- H1ステージ
- H2ステージ
- S1ステージ
- S2ステージ
最も回復に近いステージがS2で、最も重症のステージがA1です。胃潰瘍のステージは順に悪化していくわけでなく、S1からA1に悪化することもあります。
ここではそれぞれのステージの症状の特徴について解説します。
A1ステージ
A1ステージは活動期(active stage)の1段階目で、潰瘍が最も活発に活動している急性期となります。
潰瘍ができてすぐは出血や血の塊がみられることがあり、潰瘍底は白苔に覆われている様子が確認できます。また潰瘍の周辺がむくんで膨らんだ状態になっているのも特徴です。
この時期は食後少し時間が経つとみぞおちや背中に痛みが生じやすく、軽い食事であれば逆に痛みが和らぐことがあります。
A2ステージ
A2ステージは活動期(active stage)の2段階目で、A1ステージよりも症状が軽くなった状態です。
A1ステージで見られていた潰瘍底の白苔はより綺麗な状態になり、出血や血の塊がみられなくなります。潰瘍周辺のむくみは減っていくものの、周辺に発赤が少し見られる状態です。
またA1ステージよりは症状が改善されるものの、活動期ではあるため、食後少し時間が経過した時に起こるみぞおちや背中の痛みはまだ残っている場合が多いです。
H1ステージ
H1ステージは治癒過程期(healing stage)の1段階目で、潰瘍の治癒が始まった時期です。
潰瘍やむくみが少しずつ小さくなり、周辺に赤色の再生上皮(傷ついた粘膜に新しくできる上皮)がみられるようになります。また活動期にみられていた食後のみぞおちや背中の痛みは消失していることが多いです。
H3. H2ステージ
H2ステージは治癒過程期(healing stage)の2段階目で、H1ステージよりもさらに潰瘍の治癒が進んだ状態です。
潰瘍はさらに小さくなり、周辺はほぼ再生上皮に置き換わっています。
S1ステージ
S1ステージは瘢痕期(scarring stage)の1段階目で、潰瘍が治る直前の時期です。
潰瘍はほとんど消失しており、赤色の潰瘍の痕を再生上皮が覆っています。この時期にはもうほとんど痛みがありません。
S2ステージ
S2ステージは瘢痕期(scarring stage)の2段階目で、完治に最も近い状態です。
S1ステージで見られていた瘢痕が白色に変わり、症状もほとんどありません。
胃潰瘍の原因

胃潰瘍の主な原因として、以下の6つが挙げられます。
- ピロリ菌感染
- ストレス
- 非ステロイド性抗炎症薬
- 胃酸の過剰分泌
- 飲酒・喫煙・コーヒー
- 不規則な食生活や刺激の強い食事の摂取
ここでは上記6つの原因についてそれぞれ解説します。
ピロリ菌感染
ピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌で、胃潰瘍の原因の一つです。
この細菌はウレアーゼという酵素を分泌し、胃の中でアンモニアを生成することで胃酸を中和して生存し続けます。この過程で胃粘膜を刺激して慢性胃炎や萎縮性胃炎などの炎症を引き起こし、最終的に胃潰瘍を発症させることがあるのです。
ピロリ菌は主に免疫機能が確立されていない幼少期に感染することが多く、感染経路は口から口、または汚染された食べ物や水を介する経口感染が多いです。
感染していても無症状の人も多いですが、長期間放置すると胃潰瘍だけでなく、胃がんなどの命にかかわる疾患の発症リスクも高まります。定期的に検査を受け、なるべく早めにピロリ菌除菌治療を行うことが推奨されます。
ストレス
ストレスは胃潰瘍の発症リスクを高める要因の一つとされています。
過度な精神的・身体的ストレスが続くと、自律神経のバランスが崩れ、胃酸の分泌が過剰になったり胃の血流が低下したりします。その結果、胃粘膜の防御機能が低下し、潰瘍が発生しやすくなるのです。
またストレスがかかると食生活が乱れたり、喫煙や飲酒の習慣が増えたりすることで、さらに胃の状態が悪化することがあります。特に仕事のプレッシャーや不規則な生活習慣が多い現代社会では、ストレスによる胃の不調を抱える人が増えています。
ストレスを軽減するためには、適度な運動やリラックスする時間を確保し、バランスの取れた食生活を意識することが重要です。
非ステロイド性抗炎症薬
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、痛みや炎症を抑えるために広く使用される薬ですが、長期間使用すると胃潰瘍の原因となることがあります。
非ステロイド性抗炎症薬は、プロスタグランジンという物質の生成を抑えることで炎症を鎮めますが、同時に胃の粘膜を保護したり胃酸分泌を抑制したりする働きも低下させてしまいます。その結果、胃の防御機能が弱まり、胃壁が胃酸によるダメージを受けやすくなってしまうのです。
非ステロイド性抗炎症薬を服用している人はそうでない人と比べると、胃潰瘍の発生率は約10倍も多くなるといわれています。高齢者や慢性的に鎮痛薬を服用している方は特に注意が必要です。
胃酸の過剰分泌
胃酸は食物の消化を助ける重要な役割を果たしますが、過剰に分泌されると胃の粘膜を傷つけ、胃潰瘍を引き起こす原因となります。胃酸分泌が増える主な要因にはストレス、刺激の強い食事、過度な飲酒などが挙げられます。
特にストレスは自律神経を乱し、胃酸の過剰分泌の原因になりやすいため、リラックスできる環境を整えることが大切です。
飲酒・喫煙・コーヒー
飲酒や喫煙、コーヒーの摂取は胃潰瘍のリスクを高める要因の一つです。
アルコールは胃の粘膜を直接刺激し、炎症を引き起こしやすくします。特に強いアルコールや空腹時の飲酒は胃の負担が大きくなり、粘膜が傷つきやすくなります。
喫煙も、胃の血流を悪化させて胃粘膜の修復を妨げ、胃潰瘍の治りを遅らせる要因となるため注意が必要です。またニコチンが胃酸の分泌を促進するのも、胃粘膜への負担を増やす原因となります。
コーヒーに含まれるカフェインも胃酸の分泌を促進するため、過剰な摂取は胃粘膜の炎症を悪化させる可能性があります。
胃の健康を守るためには、なるべくお酒やたばこ、カフェインは控え、胃にやさしい飲み物に切り替えることが大切です。
不規則な食生活や刺激の強い食事の摂取
不規則な食生活や刺激の強い食事の摂取も、胃潰瘍の大きな原因となります。
胃に悪影響を与える食習慣として、具体的に以下が挙げられます。
- 食べ物をよく噛まずに食べる
- 就寝直前に食事をする
- 食べすぎ・飲みすぎ
食事をとる時間がバラバラになるのも、胃への負担を増やす原因となるため注意が必要です。空腹の時間が長く続いた後に食べると、胃酸が急激に分泌され、胃の負担が増大します。
また唐辛子や香辛料の多い料理、酸味や塩分が強い食品、脂っこい食べ物などは胃を刺激して胃酸の分泌を促すため、胃の炎症を悪化させる原因になります。
胃潰瘍の予防や症状の改善のためには、食生活を見直し、規則正しい時間に消化の良い食事を心がけることが大切です。
胃潰瘍の検査方法

胃潰瘍の主な検査方法は3つ挙げられます。
- 胃X線検査
- 胃内視鏡検査
- ピロリ菌検査
ここでは上記3つの検査方法についてそれぞれ解説します。
胃X線検査
胃X線検査はバリウムを使って胃の形状や粘膜の異常を確認する方法で、『バリウム検査』とも呼ばれています。造影剤であるバリウムと発泡剤を飲み、胃を膨らませた状態でX線撮影を行う検査方法です。
胃X線検査は比較的簡便で、胃カメラを飲み込む胃内視鏡検査と比べると負担が少ないことがメリットですが、潰瘍の状態を詳細に観察するには限界があります。そのため異常が疑われる場合は、より精密な胃内視鏡検査が推奨されることが多いです。
胃内視鏡検査
胃内視鏡検査は『胃カメラ検査』とも呼ばれるもので、内視鏡で直接胃の内部を観察することで、潰瘍の有無や状態を詳細に確認できる検査方法です。口または鼻から細い内視鏡を挿入し、カメラを通じて胃の粘膜を観察します。
潰瘍の大きさや形状、出血の有無などを確認できるため、胃X線検査よりも正確な診断が可能です。また検査中に組織の一部を採取(生検)し、ピロリ菌の有無や悪性の可能性(胃がんの疑い)を調べることもできます。
胃内視鏡検査はX線検査に比べてより正確な診断が可能ですが、体への負担がやや大きく、検査時の不快感を伴うことがデメリットです。ただし、近年では鎮静剤を使用することで苦痛を軽減する方法も選択できるようになっています。
ピロリ菌検査
ピロリ菌検査はピロリ菌への感染有無を調べる検査方法で、主に以下の6つの方法があります。
| 分類 | 検査名 | 検査方法 |
|---|---|---|
| 内視鏡を使う検査方法 | 迅速ウレアーゼ試験法 | ピロリ菌が持つ『ウレアーゼ』という酵素の活性を利用した検査方法 |
| 鏡検法 | 内視鏡で採取した胃粘膜の組織を特殊な薬剤で染色し、顕微鏡で直接観察する検査方法 | |
| 培養法 | 内視鏡で採取した胃粘膜の組織を5~7日ほど培養させて判定する検査方法 | |
| 内視鏡を使わない検査方法 | 尿素呼気検査法 | ピロリ菌が尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解する働きを利用し、呼気中の二酸化炭素の比率からピロリ菌の有無を確認する検査方法 |
| 抗体検査法 | 血液や尿を採取し、ピロリ菌に感染した時にできる抗体の有無を調べる検査方法 | |
| 抗原検査法 | 糞便中のピロリ菌の抗原の有無を調べる検査方法 |
検査で陽性判定が出たら、薬物によるピロリ菌の除菌治療を行うことが推奨されます。
胃潰瘍の治療方法

胃潰瘍の治療方法は、ピロリ菌の除菌治療と内視鏡手術の2つが挙げられます。
- ピロリ菌の除菌治療
- 胃酸の分泌を抑える薬1種類と抗菌薬2種類の計3剤を1日2回、7日間服用する治療方法。7日間服用後、8週間以上経過後に判定試験を行い、除菌ができていなければ二次除菌治療を行う。
- 内視鏡手術
- 出血を起こしている場合は電気メスやクリッピング術による止血、止血ができない場合は外科手術を行う。
胃潰瘍はその状態に至るまでの過程が人それぞれのため、その原因・状態に応じた治療が必要です。
例えばピロリ菌に感染している場合はピロリ菌の除菌治療を優先し、出血を起こしている場合は内視鏡による止血が必要になります。
また生活習慣が原因で炎症が起きている場合は、生活習慣指導が行われる場合もあります。
まとめ
胃潰瘍は活動期(active stage)、治癒過程期(healing stage)、瘢痕期(scarring stage)の3つのステージがあり、さらにそれを2段階に分けた計6つのステージに分けられます。
主に強い症状が出るのは活動期にあたるA1ステージとA2ステージです。治癒過程期のH1・H2ステージや瘢痕期のS1・S2ステージではほとんど症状は見られません。
胃潰瘍は自覚症状が少ない方もいるため、早期発見・治療のためには定期的に検査を受けることが大切です。
『大沼田メディカルクリニック』では、安全かつ痛みの少ない内視鏡検査を実施しています。胃潰瘍の大きな原因の一つでもあるピロリ菌の検査にも対応しているため、胃の健康状態が心配な方はぜひ当院までご相談ください。
人気記事
カテゴリー
このコラムについて
当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。
現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ご予約・お問い合わせ
常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。
8:30〜12:30 / 15:30〜19:00
休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日