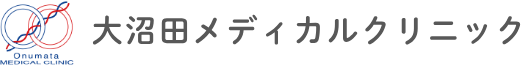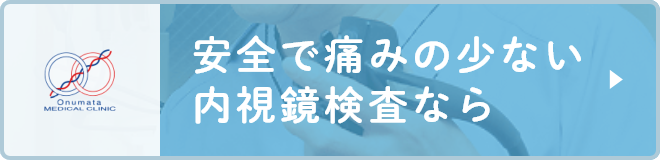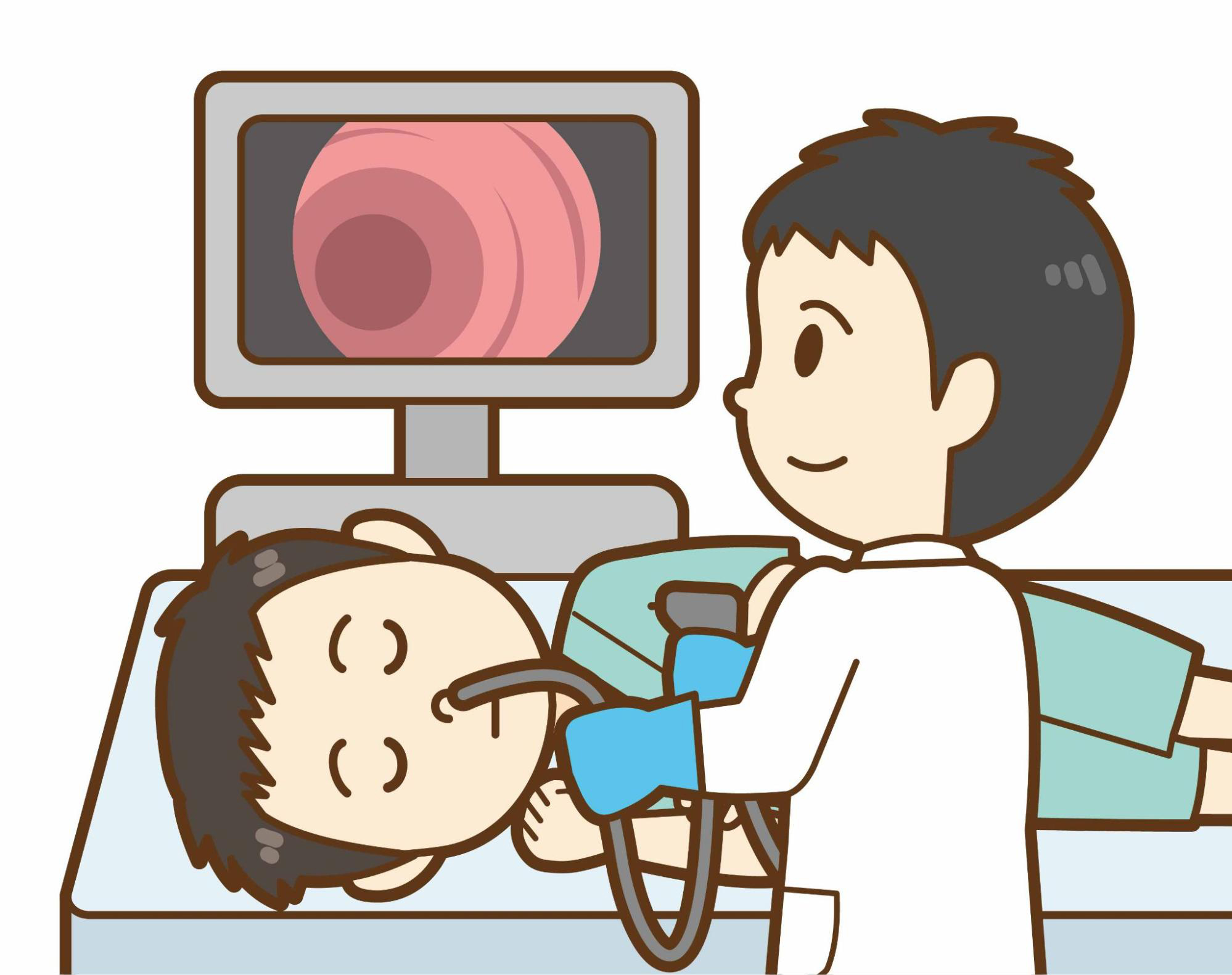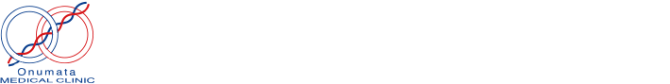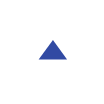ピロリ菌除菌治療で飲んではいけない薬は?治療中の注意点も解説

目次
ピロリ菌の除菌治療は、内服薬計3剤を一週間服用して行います。このときに使用される薬の種類は、胃酸の分泌を抑える薬と抗菌薬です。
またピロリ菌の除菌治療にあたって一緒に飲むことができない薬もあるため、普段から服用している薬がある方は注意しなくてはいけません。
この記事では、ピロリ菌の除菌治療中に飲んではいけない薬や注意が必要な薬について解説します。ピロリ菌除菌治療の注意点もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
ピロリ菌とは

ピロリ菌は正式名称を『ヘリコバクター・ピロリ菌』といい、胃の中に長年住み着く細菌の一種です。主に口から感染することが多く、日本では家庭内での食器の共有や口移しなどにより感染するケースが多いといわれています。
ピロリ菌に感染すると胃炎を引き起こし、腹痛や胸やけ、吐き気などさまざまな症状を引き起こす原因になります。
ここではピロリ菌の特徴やピロリ菌の感染経路、ピロリ菌に感染すると起こる症状や疾患などについて見てみましょう。
ピロリ菌の特徴
ピロリ菌は体が細長くらせん状をしており、体の片側に数本のヒゲ(べん毛)を持っている細菌です。体の中にピロリ菌が侵入すると、胃の中でべん毛を素早く回転させ、自由自在に胃粘膜の表面を動き回ります。
このようにピロリ菌が動き回る際に胃粘膜や胃壁が傷つけられるため、胃壁が胃酸の影響を受けやすくなってしまうのです。その結果、胃粘膜に炎症が起き、胃痛や胸やけといったさまざまな症状が起こる原因になります。
ピロリ菌の感染経路
ピロリ菌の感染経路は主に3つ挙げられます。
- 不衛生な環境
- 経口感染
- 医療現場での殺菌・消毒不足
海外の発展途上国や衛生管理が行われていない地域では、便や虫に触れた井戸水からピロリ菌に感染する場合があります。しかし日本ではライフラインがしっかり整備されており、高水準の衛生環境が整っているため、水道水が原因でピロリ菌に感染する可能性はほとんどありません。
また医療現場での殺菌・消毒不足についても、海外で実際に確認された例がありますが、日本の医療機関では器具の消毒・殺菌に関するガイドラインが定められています。そのため、日本の医療機関での治療が原因で感染するリスクは少ないと考えてよいでしょう。
現在の日本で最も多いと考えられている感染原因・感染経路は、自宅での経口感染です。免疫機能がまだ十分ではない幼児期に親からの口移しや食器の共有などにより、家庭内でピロリ菌に感染する場合があります。
免疫機能が発達した成人で感染する確率は低いです。
ピロリ菌に感染すると起こる症状・疾患
ピロリ菌に感染しただけでは症状が現れない場合も多いですが、感染期間が長期にわたり、胃粘膜が傷つけられ続けると慢性胃炎を引き起こすことがあります。
慢性胃炎とは、胃粘膜の炎症が数か月から数年単位で続く状態で、主に以下のような症状がみられます。
- 胃痛
- 胃もたれ
- 胸やけ
- 吐き気
- 食欲不振など
症状が出やすい人もいれば全く症状が出ない場合もあり、検査で発覚するというケースも珍しくありません。
また慢性胃炎が長期にわたると、胃粘膜が薄くなり萎縮した状態になる『萎縮性胃炎』を引き起こすことがあります。
さらにその状態から悪化すると、胃粘膜が腸の粘膜のような状態になる『腸上皮化生』が起こることがあり、胃がんのリスクが高まるため注意が必要です。
そのほかにも、ピロリ菌に感染すると起こり得る症状・疾患として以下が挙げられます。
- 胃・十二指腸潰瘍
- 胃MALTリンパ腫
- 特発性血小板減少性紫斑病
- 胃過形成性ポリープ
- 機能性ディスペプシア
- 鉄欠乏性貧血など
上記のような疾患は無症状のまま進行することもあるため、ピロリ菌感染の疑いがある方は定期的に検査を受けたり除菌治療を行ったりすることをおすすめします。
ピロリ菌の除菌治療方法と使用する薬

ピロリ菌の除菌治療は一次除菌と二次除菌の二段階に分けられ、胃酸の分泌を抑える薬1種類と抗菌薬2種類の計3剤を1日2回、7日間継続して服用して行います。
ここでは一次除菌と二次除菌それぞれで服用する薬の種類や除菌の判定方法、除菌成功率などについて解説します。
一次除菌
一次除菌では以下の薬を1日2回、7日間継続して服用します。
- 胃酸の分泌を抑える薬1種類(プロトンポンプ阻害薬)
- 抗菌薬2種類(アモキシシリン、クラリスロマイシン)
飲み忘れると除菌成功率が低下してしまうため、カレンダーや記録表なども利用して7日間正しく服用しましょう。
二次除菌
一次除菌でピロリ菌を除菌できなかった場合、二次除菌を行います。二次除菌では、一次除菌の一部の薬を変えて7日間継続して服用します。
- 胃酸の分泌を抑える薬1種類(プロトンポンプ阻害薬)
- 抗菌薬2種類(アモキシシリン、メトロニダゾール)
抗菌薬の組み合わせについては、病院によって異なる場合があります。
除菌の判定
ピロリ菌の除菌治療では、7日間服用後、8週間以上空けてから除菌判定を行う必要があります。除菌判定方法はいくつか種類がありますが、尿素呼気試験法を行うケースが多いです。
尿素呼気試験法は、ピロリ菌の酵素であるウレアーゼの活性を利用した検査方法です。ウレアーゼは尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解する働きがあるため、呼気中の二酸化炭素の割合が多くなります。
検査方法は専用の容器に息を吹き込むだけで良いため、患者さんにかかる負担が少ない特徴があります。
除菌の成功率
ピロリ菌の除菌成功率は、一次除菌で約75%、二次除菌で約95%といわれています。
上記は正しく薬を服用した場合の成功率となっているため、薬を飲み忘れてしまったり自己判断で薬を飲むのを中止したりすると、除菌できない可能性が高まるため注意が必要です。
薬を正しく服用していれば、二次除菌まででほとんどの場合成功すると報告されています。
ピロリ菌除菌で飲んではいけない薬・注意が必要な薬

ピロリ菌除菌では内服薬を服用するため、薬の飲み合わせには注意が必要です。
ここではピロリ菌の除菌治療薬と一緒に飲んではいけない薬、注意が必要な薬について解説します。
ピロリ菌の除菌治療薬と一緒に飲んではいけない薬
ピロリ菌の除菌治療薬と一緒に飲んではいけない薬として、以下が挙げられます。
- エルゴタミン:片頭痛の薬
- スボレキサント:睡眠薬
- ピモジド:統合失調症や自閉症の薬
- タダラフィル:肺高血圧症の薬
- アスナプレビル:C型肝炎ウイルスの薬
- バニプレビル:C型肝炎ウイルスの薬
- ノミタピドメシル:コレステロール値を下げる薬
- チカグレロル:心臓病の薬
- イブルチニブ:白血病治療薬
上記はピロリ菌除菌治療中に飲むことができないため、検査前に医師に相談しておきましょう。
ピロリ菌の除菌治療薬と一緒に飲む際に注意が必要な薬
ピロリ菌除菌治療薬と一緒に飲む際に注意が必要な薬として、以下が挙げられます。
- ワーファリン:血液を固まりにくくする薬
- ジゴキシン:心臓の薬
- カルバマゼピン:けいれんの薬
- ニフェジピン:血圧の薬
- テオフィリン:喘息の薬
- アトルバスタチン:コレステロール値を下げる薬
- シンバスタチン:コレステロール値を下げる薬
- グリベンクラミド:血糖を下げる薬
- トリアゾラム:睡眠薬
- エレトリプタン:片頭痛の薬
- ベラパミル:脈をコントロールする薬
- イトラコナゾール:水虫などの真菌治療薬
- リファンピシン:結核の薬
上記の薬を服用している場合も、あらかじめ医師に相談しておきましょう。
ピロリ菌検査前に飲んではいけない薬

ピロリ菌検査前に服用すると正しい結果が出ない可能性のある薬もあります。
具体的には以下の通りです。
| 薬の分類 | 薬成分名 |
|---|---|
| 胃酸を抑える薬 | ボノプラザン |
| ランソプラゾール | |
| ラベプラゾール | |
| オメプラール | |
| エソメプラゾール | |
| 胃粘膜を保護する薬 | スクラルファート |
| エカベト | |
| 抗菌薬 | アモキシシリン |
| クラリスロマイシン | |
| レボフロキサシン | |
| 下痢止め薬 | 次硝酸ビスマス |
上記の薬は検査を受ける2週間前から服用を中止する必要があります。
ピロリ菌除菌治療の注意点

ピロリ菌除菌治療の注意点として、以下の5つが挙げられます。
- 薬の副作用が出る場合がある
- 医師の指示通りに除菌治療薬を服用する
- 避けたほうがいい食べ物・飲み物
- 気になる症状が出た場合はすぐに医師に相談する
- 除菌後も定期的に検査を受ける
ここでは上記5つの注意点についてそれぞれ解説します。
薬の副作用が出る場合がある
ピロリ菌の除菌治療では、薬の副作用が出る場合があることを理解しておきましょう。
主な薬の副作用として、味覚障害や軟便、下痢などが挙げられます。何を食べても味がわからなくなった場合、ピロリ菌の除菌治療薬による副作用の可能性があります。
症状が軽度であれば7日間薬を飲み切るのが望ましいですが、血便や強い腹痛などが現れた場合は、すぐに治療を中断して医療機関を受診しましょう。
医師の指示通りに除菌治療薬を服用する
ピロリ菌の除菌治療では、医師の指示通りに除菌治療薬を服用することが大切です。自己判断で飲むのを中止したり飲み忘れたりしてしまうと、除菌が成功しにくくなるだけでなく、薬に耐性のついたピロリ菌が現れることがあります。
薬の飲み忘れが不安な方やよく飲み忘れてしまう方は、カレンダーや記録表を利用して飲み忘れを防ぎましょう。最近は薬の服用時間を知らせるアラーム機能を搭載した薬管理アプリもあるため、そういった便利ツールもぜひ活用してみてください。
避けたほうがいい食べ物・飲み物
ピロリ菌の除菌治療中は、以下のような食べ物や飲み物は避けましょう。
| 種類 | 具体例 | 避けるべき理由 |
|---|---|---|
| アルコール | ビール、日本酒、ワイン、焼酎など | 胃酸の分泌を促進し、胃粘膜を傷つける恐れがあるため |
| カフェイン | コーヒー、紅茶、緑茶、栄養ドリンク、コーラなど | 胃酸の分泌を促進し、胃痛や胸やけなどの症状を引き起こす恐れがあるため |
| 刺激物 | トウガラシ、香辛料、わさび、キムチ、カレー、炭酸飲料など | 胃粘膜を刺激し、炎症を悪化させる恐れがあるため |
| 脂っこいもの | 揚げ物、ラーメン、脂身の多い肉、バター、生クリームなど | 消化に時間がかかる影響で胃酸が過剰に分泌されやすく、炎症を悪化させる恐れがあるため |
上記のような食べ物や飲み物は胃粘膜の炎症を悪化させる可能性があるだけでなく、治療の効果に悪影響を与える恐れがあります。除菌治療中は、消化しやすく胃に負担の少ない食事を摂取するようにしましょう。
気になる症状が出た場合はすぐに医師に相談する
ピロリ菌除菌治療中に気になる症状が出た場合は、すぐに医師に相談することが大切です。
除菌治療中は薬の副作用やアレルギー反応が出る恐れがあります。万が一腹痛や蕁麻疹、高熱などの症状が現れたら、我慢せずにすぐに医師に相談しましょう。
除菌後も定期的に検査を受ける
ピロリ菌除菌治療後も、定期的に検査を受けることが大切です。
ピロリ菌感染によって発症リスクが高まる病気がいくつかありますが、ピロリ菌を除菌できたからといって、それらの発症リスクが0になるわけではありません。
なかには自覚症状がほとんどないまま進行していく病気もあるため、除菌治療後も定期的に検査を受け、早期発見・早期治療に努めましょう。
まとめ
ピロリ菌除菌治療中に飲んではいけない薬について解説しました。今回紹介した薬を普段から服用している場合は、検査前にあらかじめ医師に相談しておきましょう。
また今回紹介したものでなくても、普段から服用している薬がある場合は、念のため医師に確認しておくと安心です。
『大沼田メディカルクリニック』では、ピロリ菌の除菌治療に対応しています。鎮静剤を使用した痛みの少ない内視鏡検査も行っているため、胃腸の健康状態が心配な方もぜひ当院までご相談ください。
人気記事
カテゴリー
このコラムについて
当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。
現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ご予約・お問い合わせ
常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。
8:30〜12:30 / 15:30〜19:00
休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日