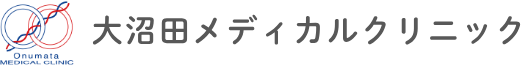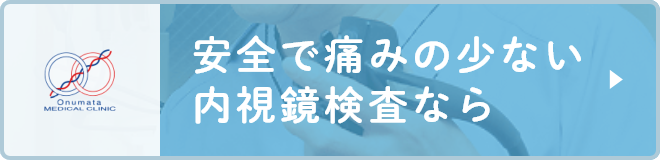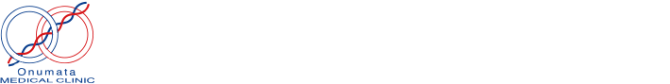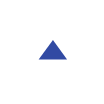ピロリ菌感染で起こる症状は?検査方法や治療方法も解説

目次
ピロリ菌は胃に長年住み着く細菌の一種で、感染するとさまざまな症状を引き起こします。具体的には慢性胃炎に伴う腹痛や体重の減少、口臭の悪化、げっぷやおならの増加などです。
この記事では、ピロリ菌に感染した時に起こる症状について詳しく解説します。ピロリ菌感染が引き起こす疾患やピロリ菌の検査・治療方法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
ピロリ菌とは

ピロリ菌は胃に長年住み着く細菌の一種で、正式名称を『ヘリコバクター・ピロリ菌』といいます。ヘリコは『らせん』、バクターは『細菌』、ピロリは胃の出口を表す『ピロルス』に由来しています。
胃には強い酸性を持つ胃酸の影響があるため、通常の細菌は生息できません。しかしピロリ菌には胃酸を中和してアルカリ性優位の環境にする『ウレアーゼ』という酵素があるため、住み着くことができるのです。
ピロリ菌の感染経路ははっきりとわかっているわけではありませんが、免疫機能が十分ではない幼少期に親からの口移しで感染する可能性があるとされています。
またピロリ菌に感染しただけでは症状は出ませんが、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の患者さんにはピロリ菌に感染している人の割合が高いことから、これらの病気の発症に関係していると考えられています。
ピロリ菌感染の主な症状
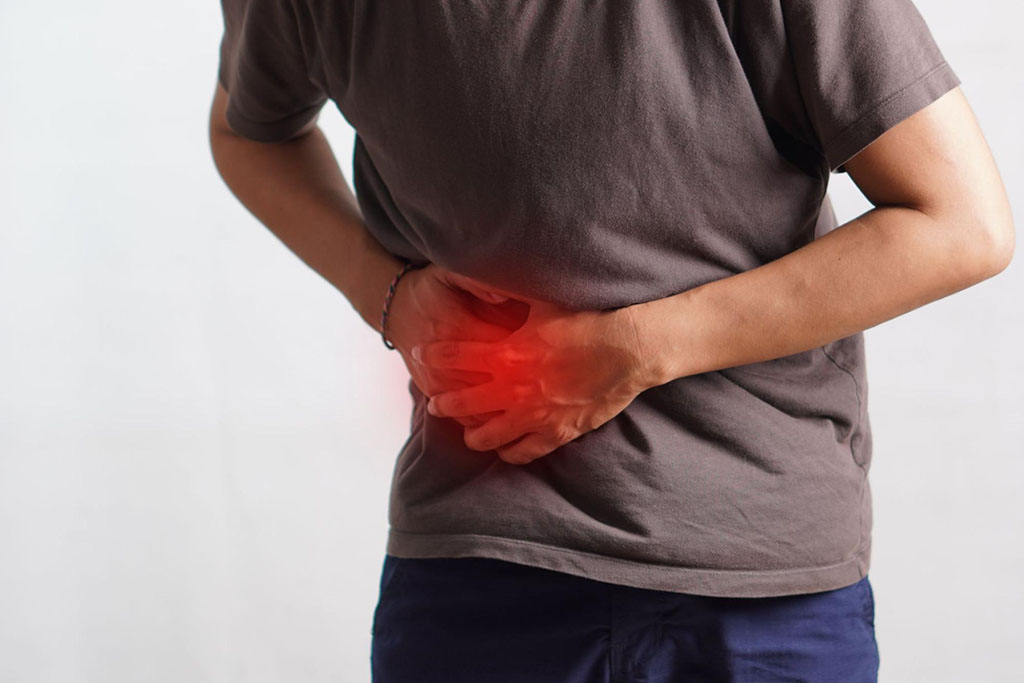
ピロリ菌感染の主な症状として以下が挙げられます。
- 慢性胃炎に伴う症状
- 口臭の悪化
- げっぷやおならの増加
ここでは上記3つの症状についてそれぞれ解説します。
慢性胃炎に伴う症状
ピロリ菌感染は慢性胃炎を引き起こすことがあります。
慢性胃炎は数か月から数年単位で胃の炎症が続く状態のことで、主に以下のような症状が現れます。
- 胃痛
- 胸やけ
- 吐き気
- 食欲不振
- 胃のむかつき
- 腹部膨満感
胃の痛みや不快感、胃もたれなどが主な症状ですが、胃酸の分泌異常によって胸やけや吐き気を起こすこともあります。
また胃の調子が悪くなることで食欲不振になり、体重減少につながることもあるため注意が必要です。
口臭の悪化
ピロリ菌感染は口臭悪化の原因となることがあります。ピロリ菌はアンモニアなどの有害物質を作り出すため、これが口臭に悪影響を及ぼすのです。
口臭の悪化はピロリ菌だけが原因になるわけではありませんが、他に歯周病などの原因が見当たらず、歯磨きや口臭対策をしても改善しない場合はピロリ菌の影響が疑われます。
げっぷやおならの増加
ピロリ菌に感染するとげっぷやおならが増加することがあります。これはピロリ菌の感染によって慢性胃炎や過敏性腸症候群などが起こるためです。
また大腸がんの進行により便秘が悪化すると、おならの回数が増えることもあります。
げっぷやおならの頻度が急に増えた場合はピロリ菌が影響している可能性があるため、胃腸の健康状態を確認しましょう。
ピロリ菌感染の症状が出るのはいつから?

インフルエンザやノロウイルスなどとは異なり、ピロリ菌には症状が出るまでの期間(潜伏期間)は存在しません。ピロリ菌に感染したからといって全員に必ず症状が現れるわけでなく、さらに症状が現れる場合も感染してから年単位の時間がかかるためです。
またピロリ菌は小児期に感染することがほとんどで、大人になってから感染するケースは少ないと考えられています。
ピロリ菌感染が引き起こす疾患
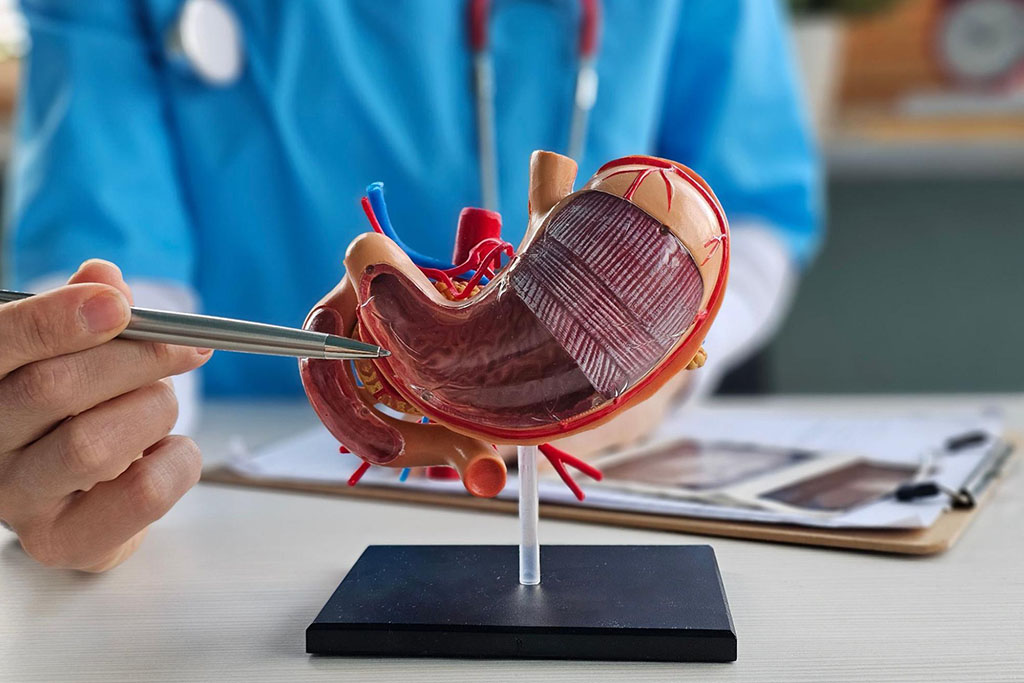
ピロリ菌感染が引き起こす疾患として以下が挙げられます。
- 慢性胃炎
- 消化性潰瘍
- 萎縮性胃炎
- 胃がん
- その他の病気
ここでは上記についてそれぞれ解説します。
慢性胃炎
ピロリ菌に感染すると慢性胃炎を引き起こすことがあります。
慢性胃炎は胃の中の炎症が広範囲に広がり、数か月から数年単位で慢性的に継続する病気です。
ピロリ菌が原因で起こる慢性胃炎は『ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎』と呼ばれます。胃痛や胸やけ、吐き気、食欲不振などが主な症状で、悪化すると胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの他の病気の原因にもなるため注意が必要です。
慢性胃炎単体の発症で急激に症状が悪化することは少ないですが、栄養バランスの偏った食生活や睡眠不足、ストレス、過度な飲酒・喫煙などの生活習慣の影響で重症化することがあります。
消化性潰瘍
ピロリ菌が排出する毒素の影響で胃粘膜に炎症が起きると、消化性潰瘍が生じることがあります。
消化性潰瘍は胃や腸の表面を守る粘膜に穴が開くことで生じるもので、主な症状は以下の通りです。
- 腹部膨満
- 吐き気・嘔吐
- 食欲不振
- 胸やけ
- みぞおちの鈍い痛み
他の消化器疾患の場合、食事を食べると症状が悪化するものが多いですが、消化性潰瘍は食事をとることで逆に症状が和らぐことが多いです。
潰瘍が悪化すると出血を伴うようになり、便に血液が混じったり吐血したりする場合があります。
萎縮性胃炎
ピロリ菌感染による慢性胃炎が悪化すると萎縮性胃炎に移行することがあります。
萎縮性胃炎は、慢性胃炎の長期化によって胃の粘膜が萎縮した状態です。胃粘膜が萎縮すると食べ物を消化する機能が低下し、以下のような症状が現れます。
- 胃もたれ
- 食欲不振
- 胸やけ
- げっぷ
- 胃の痛み
- 吐き気
- 腹部膨満感
萎縮性胃炎で現れる症状の強さは胃粘膜の萎縮の程度とは無関係で、個人差があります。
強く症状が現れる方はストレスなどの心因性の問題が絡んでいることがあるため、ストレスを抱え込みやすい方は特に注意が必要です。
中には胃粘膜に炎症が起きているにもかかわらず自覚症状がない場合もあり、健康診断や人間ドックの検査で初めて自覚する方も少なくありません。
胃がん
ピロリ菌の感染によって胃粘膜が萎縮した状態が続くと、胃がんの発症リスクが高まるため注意が必要です。
胃がん発症者の約90%以上にピロリ菌感染歴があることもわかっており、1994年にはWHO(世界保健機関)によって、タバコやアスベストと同じ分類である『確実な発がん因子』として認められています。
胃がんは初期段階では無症状のことが多いですが、進行すると以下のような症状が現れます。
- 腹痛
- 食欲不振
- みぞおち周辺の痛み・不快感
- 吐血・下血・貧血
胃がんにはステージ1からステージ4まで4つのステージがあり、ステージ1では自覚症状がほとんどありません。ステージ1の段階で病変を適切に切除すれば治る可能性が高いため、早期発見・治療が重要になります。
その他の病気
ピロリ菌感染が原因で引き起こされるその他の病気として、以下が挙げられます。
いずれもピロリ菌除菌により症状改善がみられる可能性があります。
胃マルトリンパ腫
白血球の中にあるリンパ球が、がん化する病気。
無症状の場合が多い。まれに腹痛、腹部の不快感、吐血、全身のだるさなどがみられる場合もある。
特発性血小板減少性紫斑病
血液中の血小板を破壊する抗体が生成されることで、血小板数が減少してしまう病気。
症状は皮下出血、歯肉出血、鼻出血、下血、血尿頭蓋内出血など。
機能性胃腸症
胃の異常や病変が認められないにもかかわらず、胃の症状が現れる病気。
症状は吐き気、胸やけ、みぞおちの痛み、食後の胃もたれ、げっぷなど。
胃過形成性ポリープ
胃粘膜の炎症により発生するポリープ。
基本的には無症状。同時発症している慢性胃炎による胃もたれ、不快感、食欲不振などがみられる場合もある。
ピロリ菌感染の検査方法

ピロリ菌に感染しているかどうかを確認するための検査方法には、以下のようにいくつかの種類があります。
- 内視鏡を使う検査方法
- 迅速ウレアーゼ試験
- 鏡検法
- 培養法
- 内視鏡を使わない検査方法
- 尿素呼気試験
- 抗体検査
- 抗原法
ここでは上記6種類の検査方法についてそれぞれ解説します。
内視鏡を使う検査方法
内視鏡を使う検査方法には以下の3つの種類があります。
- 迅速ウレアーゼ試験
- ピロリ菌が持つ酵素『ウレアーゼ』の特性を利用して調べる検査方法
- 鏡検法
- 採取した胃粘膜の組織に特殊な染色をしてピロリ菌を探す検査方法
- 培養法
- 採取した胃粘膜を5~7日程度培養して判定する検査方法
ここでは上記3つの検査方法についてそれぞれ解説します。
迅速ウレアーゼ試験
迅速ウレアーゼ試験は、ピロリ菌が持つ『ウレアーゼ』という酵素の特性を利用した検査方法です。
内視鏡で採取した組織に試薬を投与し、色の変化によってピロリ菌の有無を確認します。
この検査方法は検査結果が一目でわかり、さらに15分ほどで結果が出るメリットがあります。
ただしピロリ菌のいない部分を採取してしまうと、実際はピロリ菌に感染しているのに陰性になる可能性がある点には注意が必要です。
鏡検法
鏡検法は、内視鏡で採取した胃粘膜の組織に特殊な染色をして、それを顕微鏡で直接見てピロリ菌の有無を確認する検査方法です。
ピロリ菌の感染診断はもちろん、がんの診断や炎症の程度の診断も同時に行えるメリットがあります。
培養法
培養法は、内視鏡で採取した胃粘膜を5~7日程度培養して判定する検査方法です。
ピロリ菌に感染している場合は増殖するため、判定しやすくなります。
この検査方法でピロリ菌がみられなかった場合は、正しく陰性であると判断できる可能性が高いメリットがあります。
ただし感度がそれほど高くないため、実際には陽性であるにもかかわらず、陽性ではないという結果が出てしまうことがある点には注意が必要です。
内視鏡を使わない検査方法
内視鏡を使わない検査方法には以下の3つの種類があります。
- 尿素呼気試験
- 容器に息を吹き込み、その呼気に含まれる炭酸ガスの量によって判定する検査方法
- 抗体検査
- ピロリ菌が作り出す抗体の有無を調べる検査方法
- 抗原法
- 糞便中のピロリ菌の抗原の有無を調べる検査方法
ここでは上記3つの検査方法についてそれぞれ解説します。
尿素呼気試験
尿素呼気試験は、容器に息を吹き込み、その呼気に含まれる二酸化炭素の量によって陽性・陰性を判定する検査方法です。
ピロリ菌が持つウレアーゼという酵素は、尿素を分解してアンモニアと二酸化炭素を生成する特徴があります。そのためピロリ菌に感染している人は二酸化炭素の割合が高くなるため、陽性と判定できます。
正確に検査を行うためには検査4時間以内に食事をしていないこと、検査2時間以内に飲水していないことなどの条件がありますが、身体への負担がかなり少ない検査方法です。
抗体検査
抗体検査は、ピロリ菌が作り出す抗体の有無を調べる検査方法です。
血液や尿から抗体を測定する方法で、測定した値が一定以上の場合にピロリ菌感染の可能性が高いと判断できます。ただしピロリ菌の抗体が陽性であると診断された場合、すぐに除菌治療が行えるわけではない点は理解しておきましょう。
抗体はピロリ菌そのものではないため、他の検査方法で確定診断を行ってから治療します。
抗原法
抗原法は、糞便中のピロリ菌の抗原の有無を調べる検査方法です。
身体への負担がないため、小児でも検査を受けられます。検査結果の信頼度が高く、感染有無はもちろん、除菌の効果判定検査にも使われる検査方法となっています。
ピロリ菌感染の治療方法

ピロリ菌感染の除菌治療では、抗生物質の内服薬を使用します。
治療は2段階あり、一次除菌療法で除菌できなかった場合は二次除菌療法を行う必要があります。
一次除菌療法
一次除菌療法では胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬と2種類の抗生剤(アモキシリン、クラリスロマイシン)の3種類の薬を1日2回、7日間継続して服用します。
その後、8週間後以降に尿素呼気試験または抗原法により除菌判定を行い、陰性であれば除菌成功となります。
一次除菌療法の除菌成功率は約70〜90%です。
二次除菌療法
二次除菌療法では、一次除菌療法と同じ種類の胃酸を抑える薬と抗菌薬、一次除菌療法とは別の抗菌薬の合計3種類の薬を1日2回、7日間服用します。
一次除菌療法と同様に除菌判定を行います。二次除菌療法の除菌成功率は約95%です。
再び陽性結果が出てしまった場合は、三次除菌療法が必要となります。
まとめ
ピロリ菌に感染すると慢性胃炎を引き起こし、胃の痛みや不快感、胃もたれなどの症状が現れることがあります。また、ピロリ菌の感染は消化性潰瘍や萎縮性胃炎、胃がんなどの原因にもなり得るため、なるべく早めに除菌治療を行うことが望ましいです。
ピロリ菌に感染しただけでは症状が現れないことも多いため、定期的に検査を受けて早期発見に努めましょう。
『大沼田メディカルクリニック』では、内視鏡検査と血液検査を組み合わせたピロリ菌検査を行っています。内視鏡による精密検査で消化器疾患の早期発見も可能なため、ピロリ菌検査を検討中の方はぜひ当院までご相談ください。
人気記事
カテゴリー
このコラムについて
当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。
現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ご予約・お問い合わせ
常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。
8:30〜12:30 / 15:30〜19:00
休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日