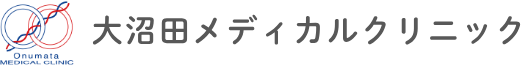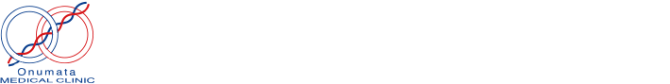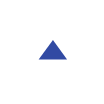高血圧になると起こる症状は?合併症のリスクや過ごし方のポイントを解説

目次
高血圧は健康に良くない状態ですが、具体的にどのように身体に悪影響を及ぼすのかよくわかっていない方も多いのではないでしょうか。高血圧は放っておくと動脈硬化や心筋梗塞といった合併症を引き起こすリスクが高まるため、早めに気づいて対処することが大切です。
この記事では、高血圧の主な症状について詳しく解説します。高血圧の原因や血圧が高いときの過ごし方のポイントなどもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
高血圧の主な症状は?

高血圧とは、その文字の通り血圧が高い状態のことです。
日本高血圧学会の高血圧診断基準では、『診察室での収縮期血圧(最大血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(最小血圧)が90mmHg以上の場合』と定義されています。これは診察室での測定の場合で、自宅で測る家庭血圧の場合は診察室よりも5mmHg低い基準となっています。
また高血圧は日本の生活習慣病死亡に最も大きく影響する要因です。高血圧は数十年の間に大きく減少してはいるものの、未だに20歳以上の国民のおよそ2人に1人は高血圧とされています。
血圧とは
血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の内壁を押す圧力のことです。
血圧に影響する要因には以下が挙げられます。
- 心拍出量(心臓が1回の拍動で全身に送り出す血液量)
- 血管のしなやかさ
- 血管抵抗(血液が血管に流れ込む際の末梢血管の抵抗力)
- 血液の粘度
- 腎臓や神経の働き
さらにこれらの要因には精神的ストレスや食事、運動などが影響するため、血圧は常に一定に保たれているわけではありません。
例えば運動すると一時的に血圧が上昇することがありますが、その後安静にしていれば自然と下がります。これは正常な血圧の変化ですが、高血圧の場合は運動をしていなくても血圧が高い状態が続きます。血圧が高い状態が続くと心臓や血管に負担がかかるため、さまざまな症状を引き起こすのです。
高血圧の主な症状
高血圧の主な症状として、頭痛やめまい、肩こりなどが挙げられます。
しかし、多少血圧が高い程度では自覚症状が現れないことも多く、上記のような症状は高血圧でなくても現れやすいものです。そのため高血圧はなかなか気づきにくく、治療せずに放っておかれてしまうことが少なくありません。
また、高血圧の状態が長く続くと、動悸や息切れ、むくみ、嘔吐、痙攣などの症状が現れる場合があります。これほどの症状が出るときにはすでに心臓や血流に深刻な影響が出始めている段階のため、すぐに医療機関を受診しましょう。
高血圧になりやすい人の特徴は?セルフチェック
高血圧になりやすい人の特徴として以下が挙げられます。
- BMIが25以上(肥満体型)
- 親族に高血圧の人がいる
- 糖尿病
- 脂質異常症
- 喫煙習慣がある
- 塩分の多い食事を好む
- アルコールをよく飲む
- ストレスを感じやすい
- 1日の運動時間が30分未満
上記のうち、3つ以上当てはまる場合は高血圧のリスクが高い状態です。
血圧は家庭用血圧計で測るか、人間ドックや健康診断で測ってもらいましょう。
高血圧による合併症のリスク

高血圧による合併症のリスクとして以下が挙げられます。
- 動脈硬化
- 狭心症・心筋梗塞
- 脳卒中
- 腎硬化症・慢性腎臓病
- 大動脈瘤
- 心不全
- 眼底出血
ここでは上記7つのリスクについてそれぞれ解説します。
動脈硬化
高血圧の状態が続くと血管壁に負担がかかり、血管が徐々に固くなり弾力性が低下してしまいます。血管の弾力性が低下すると血液が流れにくくなり、全身の細胞に十分な酸素や栄養分が送れなくなるのです。
動脈硬化が進むと脳出血や脳梗塞、心不全、狭心症、心筋梗塞、大動脈瘤などさまざまな合併症の原因になります。
狭心症・心筋梗塞
高血圧の状態が続くと、狭心症や心筋梗塞を引き起こすリスクが高まります。心臓に酸素や栄養分を送る冠動脈が狭くなるのが『狭心症』、血管が完全に詰まってしまうのが『心筋梗塞』です。どちらも動脈硬化が主な原因となります。
狭心症は胸の痛みや締め付けられるような圧迫感、背中や上腹部の痛みなどが主な症状です。
心筋梗塞は脂汗が出るほどの激しい胸の痛みや圧迫感が主な症状で、狭心症とは異なり30分以上痛みが続く特徴があります。
どちらも命にかかわる危険な病気のため、早期治療が重要です。
脳卒中
高血圧状態が続き動脈硬化が進むと、脳卒中を引き起こすことがあります。
脳卒中は脳の血管が狭窄・閉塞・破裂する病気で、『脳梗塞』『脳出血』『くも膜下出血』『一過性脳虚血発作』などの種類があります。
- 脳梗塞:脳の動脈が塞がって血液が途絶え、脳が壊死してしまう病気
- 脳出血:脳内の細い血管が破れて出血する病気
- くも膜下出血:脳動脈瘤が破裂してくも膜下腔に出血が起こる病気
- 一過性脳虚血発作:脳の動脈が一時的に詰まり、短時間のみ神経症状が生じる病気
上記のような脳卒中発作はある日突然起こるため、日頃から血圧に注意することが大切です。
腎硬化症・慢性腎臓病
高血圧状態が続くと、腎臓の代謝機能が低下する腎硬化症や慢性腎臓病を引き起こすことがあります。
腎臓は血液をろ過して老廃物を取り除く働きがありますが、高血圧が長期間続くと十分にろ過ができなくなったり尿にタンパクが出るようになったりすることがあるのです。
腎障害が進行すると腎機能が低下し続け、腎臓が機能しなくなる腎不全に陥ることがあります。
大動脈瘤
高血圧は大動脈瘤を引き起こすことがあります。
大動脈瘤は大動脈の壁が膨らんだ状態で、動脈硬化や高血圧が主な原因と考えられています。
自覚症状がないまま大きくなることが多く、最悪の場合、膨らんだ部分が破裂してしまう『大動脈瘤破裂』が起こることがあるため注意が必要です。
大動脈瘤破裂は緊急手術でしか救命できない場合が多く、とても危険な状態です。
心不全
高血圧状態によって心臓に高い負荷がかかり続けると、心不全が起こることがあります。
心不全とは、心臓のポンプ機能の低下によって、全身に十分な血液を送れなくなる状態のことです。主な症状として足のむくみや息切れ、尿量の減少、体重増加などが挙げられます。
心不全を放置しておくと次第に症状が悪化し、安静時にも心不全症状や胸部の痛みが起こることがあります。
眼底出血
高血圧状態は、眼底出血や高血圧性網膜症、眼底網膜病変などの目の病気を引き起こすことがあります。これらの病気は深刻な視力障害や失明につながる場合があるため、注意が必要です。
また、眼底の病変は脳の血管状態にも深く関係しているため、これらの病気の疑いがある場合は脳出血や脳梗塞にも気を付ける必要があります。
高血圧の原因は2種類

高血圧は原因によって『本態性高血圧症』と『二次性高血圧症』の2種類に分けられます。
ここでは2種類の原因についてそれぞれ解説します。
本態性高血圧症
本態性高血圧症は原因を特定できないものを指し、高血圧の90%を占めるとされています。
本態性高血圧の要因には以下のようなものが挙げられます。
- 肥満
- 塩分摂取過多
- 運動不足
- 過剰飲酒
- 喫煙
- 精神的ストレス
- 野菜・果物不足
- 自律神経の調節異常
など
上記の通り、主に生活習慣が原因と考えられることが多いため、生活習慣の改善と並行して治療を行うことになります。
二次性高血圧症
二次性高血圧症は血圧上昇の原因がはっきりとしているものを指します。
原因となる病気には以下のようなものが挙げられます。
- 原発性アルドステロン症
- クッシング症候群(クッシング病)
- 褐色細胞腫
- 甲状腺機能亢進症
- 甲状腺機能低下症
- 腎血管性高血圧
- 腎実質性高血圧
また上記のような病気のほか、薬の作用によって高血圧が起こることもあります。
代表的なのは甘草を含む漢方薬です。甘草にはアルドステロンの分解を抑制する作用があるため、原発性アルドステロン症と似たような症状が現れることがあります。
薬の飲み合わせによって血圧が上昇することもあるため、持病の治療で薬を服用している方は注意が必要です。
血圧が高いときの過ごし方のポイント

血圧が高い時の過ごし方のポイントは以下の通りです。
- 減塩する
- 肥満を予防し適切な体重を維持する
- 定期的に運動する習慣をつける
- 野菜や果物を積極的に摂取する
- 禁酒・禁煙する
- 十分な睡眠・休養をとる
- 便秘を予防する
- 室内と外気の差を少なくする
ここでは上記8つのポイントについてそれぞれ解説します。
減塩する
塩分の摂取過多は高血圧の原因となるため、減塩を心がけることが大切です。
食塩摂取量の目標値は男性で1日8g未満、女性で1日7g未満とされていますが、高血圧気味の方は1日6g未満に抑えることが推奨されています。調味料を減塩タイプに変える、味付けを薄くするなど、食塩摂取量を抑える工夫をしてみましょう。
肥満を予防し適切な体重を維持する
高血圧は肥満の方にも多く見られるため、血圧の上昇を予防するためには適正体重を維持することが大切です。
肥満の判定基準にはBMI(体重㎏÷身長m²)が用いられており、BMI25以上は肥満と診断されます。すでに肥満気味の方は日頃の食生活や生活習慣の見直しを行い、適正体重まで減量しましょう。
人それぞれに合った減量方法があるため、自分に合った方法で健康的な体重を目指すことが大切です。
定期的に運動する習慣をつける
定期的に運動する習慣をつけることで、血流の改善が期待できます。ウォーキングやジョギング、水中運動などの有酸素運動を中心に、1日30分以上を目標に体を動かしてみましょう。
ただし高血圧の重症度や合併症の有無によって、推奨される運動量が異なるため、まずは医師にどの程度の運動ならしても良いか確認することをおすすめします。
運動中に頭がふらふらしたり、息切れが強かったりする場合は、無理せず中止して医師に相談してください。
野菜や果物を積極的に摂取する
野菜や果物に含まれるカリウムには、体内の塩分を排出する作用があります。
カリウムが多く含まれる野菜や果物としては以下のようなものが挙げられます。
| 野菜 |
|
| 果物 |
|
栄養バランスが偏ってしまうとよくないため、上記の果物や野菜も意識して取り入れつつ、バランスの整った食事を心がけましょう。
禁酒・禁煙する
お酒やたばこは高血圧や動脈硬化の原因となるため、できれば禁酒・禁煙するのが望ましいです。完全にやめるのが難しい場合は、タバコを吸う頻度やお酒を飲む量・頻度を調整し、なるべく血管に負担のかからないようにしましょう。
「禁煙したいけどなかなか辞められない」とお悩みの方は、医療の力で禁煙を目指す『禁煙外来』の受診を検討してみてください。
十分な睡眠・休養をとる
血圧を上げる要因として身体的・精神的ストレスが挙げられるため、高血圧を防ぐためには十分な睡眠と休養が重要になります。毎日規則正しい生活を送ることを心がけ、十分な睡眠時間を確保しましょう。
良質な睡眠をとるためのポイントは以下の通りです。
- 日中にできるだけ日光を浴びる
- 寝る前にスマートフォンやタブレットを見ない
- 入浴は就寝の1~2時間前までに済ませる
- リラックスできる睡眠環境を整える
上記を意識して、体をしっかり休めましょう。
便秘を予防する
便秘によっていきんでいる時間が長いと血圧が上がるため、日頃から便秘を予防しましょう。
便秘を予防する具体的な方法としては以下が挙げられます。
- 毎日朝食後に必ずトイレに行く
- 朝食前に冷水や冷たい牛乳を飲む
- 食物繊維の多い野菜や海藻類を積極的に摂取する
また運動も腸の働きを活発にさせるため、毎日の運動習慣をつけるのも有効です。
室内と外気の差を少なくする
暖かいところから寒いところに出ると血管が収縮して血圧が上がってしまうため、高血圧を防ぐにはなるべく室内と外気の差を少なくすることが大切です。
具体的な対処方法としては、冬の外出時はマフラーや手袋などの防寒具を着用する、居間・居室・便所などで暖房を活用するなどが挙げられます。
室内と外気の温度差が5度以上にならないように気を付けましょう。
まとめ
高血圧は自覚症状が少ないため気づきづらいですが、血圧が高くなりすぎると頭痛やめまい、肩こりなどの症状が現れることがあります。
さらにこれらの症状が出るだけでなく、動脈硬化や狭心症・心筋梗塞、脳卒中、心不全など全身の臓器にさまざまな悪影響が出るリスクがあるため注意が必要です。
合併症を引き起こさないためには、自宅で毎日血圧を確認する、定期的に健康診断を受けるなどが大切です。
『大沼田メディカルクリニック』では、高血圧や高脂血症などをはじめとするさまざまな病気の診断・治療に対応しています。検査による病気の早期発見も可能なため、体の不調にお悩みの方はぜひ当院までご相談ください。
人気記事
カテゴリー
このコラムについて
当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。
現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ご予約・お問い合わせ
常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。
8:30〜12:30 / 15:30〜19:00
休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日